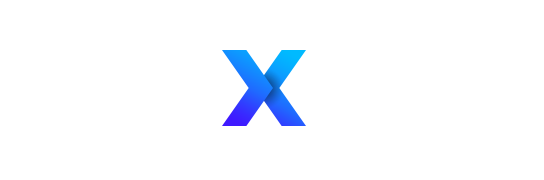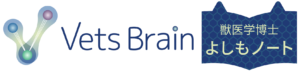本研究は、犬の癌患者のモニタリングと予後のためのツールとして、乳腺癌の雌犬におけるカルシノエンブリオニック抗原(CEA)の挙動を評価し、その診断的価値を理解することを目的とした。77頭の雌犬の血清サンプルを、G1(n=21)、対照群(健康/新生物のない雌犬)、G2(n=31)、3cm未満の非転移性乳腺癌の雌犬、G3(n=12)、3cm以上の非転移性乳腺癌の雌犬、G4(n=13)、乳腺癌とリンパ節転移のある雌犬の4群に分けた。G1ではマーカーを1回投与したが、G2、G3、G4では、乳房切除前(M0)と乳房切除後15日目(M1)に、ヒト用のELISAキットを用いてCEAレベルを測定し、リーディングではELISYS ONE humanを用いた。11匹の雌犬のグループは、乳房切除の45日後(M2)に追跡調査を行った。評価した時点での血清サンプル中のマーカー濃度の結果と、新生物の生物学的挙動および観察された臨床病理学的変化との関係を、Tukey検定により5%の有意差で評価した。ROC曲線を用いてカットオフ値を求め、検査の感度と特異性を算出し、多変量マッチング解析を行ってCEA値と臨床病理学的変数との関連を確認した。CEA値は、乳腺癌、直径3.0cm以上の転移性腫瘍、高悪性度の雌犬で、健常雌犬と比較して有意に上昇した。また、乳房切除術を受けると、血中のCEA濃度が低下し(P < 0.05)、CEA濃度が高いと予後不良因子と関連していた(P < 0.05)。このバイオマーカーは、特に侵攻性の高い腫瘍に対して良好な診断価値を示した。結論として、CEA血清濃度は、乳腺腫瘍のある雌犬ではCEA値が上昇し、乳房切除後には低下し、腫瘍の大きさ、リンパ節転移、組織学的グレードなどの予後因子と相関することから、雌犬の乳腺腫瘍の進展を効率的に追跡することができた。再発や早期転移のフォローアップにおけるCEAの診断的価値を確認するには、さらなる研究が必要である。
第17巻第4号の表紙画像
カバーイメージは、SHORT COMMUNICATION Clinical outcomes, ultrastructure and immunohistochemical features of canine high-grade olfactory neuroblastoma by Molly E. Church.
Church et al,
https://doi.org/10.1111/vco.12512.
19週間のCHOPプロトコルで治療したナイーブなB細胞リンパ腫の犬におけるフローサイトメトリーの特徴、病理組織学的診断および臨床転帰のプロスペクティブな評価
この試験は、ナイーブな犬のB細胞リンパ腫患者を、病理組織学、フローサイトメトリー(FC)、および標準化された化学療法プロトコルを用いて前向きに評価し、治療に対する反応が異なる可能性のあるこの疾患のサブセットをより明確にすることを目的としたものである。64頭のナイーブな多中心性B細胞リンパ腫の犬が、19週間の標準化されたCHOP(シクロホスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチン、プレドニゾン)化学療法プロトコルで治療を受けた。ほとんどの犬(84.3%)がびまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)と診断され、次いで結節性辺縁帯(7.8%)、小細胞型B細胞(4.7%)、バーキット様(1.6%)、濾胞性リンパ腫(1.6%)と診断された。FCでは、すべての症例でB細胞リンパ腫の診断が確定した。FCパネルで検出されたB細胞リンパ腫のサブタイプの間には、明確な表現型の違いはなかった。本研究の組織学的サブタイプは、フローサイトメトリーでの前方散乱値に幅があったが、DLBCLの全症例は469という値よりも高く、前方散乱値が低かったのは濾胞性リンパ腫とびまん性小細胞B細胞リンパ腫のみであった。DLBCLの犬は、CHOPプロトコルに対する客観的奏効率が96.3%と、非DLBCLのサブタイプ(70%、P = 0.024)よりも有意に高かった。DLBCL患者の無増悪生存期間の中央値(233日)は、他のすべての組織学的サブグループの合計値(163日、P = 0.0005)よりも有意に長かった。
組織学的断端と残存腫瘍分類法。獣医の腫瘍学におけるマージン評価を標準化するために、ヒトの腫瘍学で検証されたスキームを使用する時が来たのでしょうか?
獣医学における組織学的完全切除の定義については、コンセンサスが得られていない。様々な研究で多くの定義が用いられているが、これらは明らかな正当性を持たずに恣意的に選択されているのが現状である。組織学的完全切除を組織学的腫瘍のないマージンが0mm以上と定義する残存腫瘍分類法は、ヒトの腫瘍学では40年以上前から主要な臨床病期分類機関のすべてで使用されており、ヒトの悪性腫瘍の大部分で予後が良好であると考えられている。残存腫瘍分類法は、臨床および研究の両方で広く使用されているため、この標準化されたアプローチは、臨床医間のコミュニケーションを向上させ、外科的切除後の補助療法の選択肢についてエビデンスに基づいた意思決定を行い、患者が不必要な補助療法を受けることを最小限にし、異なる研究間で特定の腫瘍の局所制御を比較する能力を向上させます。獣医の腫瘍学において残存腫瘍分類スキームを採用すれば、同様の結果が得られる可能性が高く、組織学的に完全な切除を構成するものの定義に関して、一般開業医と専門家の両方の獣医界に蔓延している混乱を最小限に抑えることができる。
犬の肉腫に対する新たな治療アプローチ。従来の枠を超えた新しい治療法
肉腫は、間葉系由来のゲノム的に混沌とした高度に異質な腫瘍であり、変異負荷が変化する一群の腫瘍である。手術と放射線治療を組み合わせた従来の治療法は、低悪性度の小さな肉腫に効果的であり、現在も標準的な治療法として用いられています。しかし、進行した高悪性度の肉腫や再発・転移性の肉腫に対しては、全身化学療法を行っても効果が少ないため、新しい治療法の開発が求められています。19世紀に発見された “Coley’s toxins “は、免疫系を刺激する効果があることから、肉腫の治療に型破りな治療法を適用することができました。有望ではありましたが、この初期の研究は放棄され、肉腫の治療パラダイムと疾患経過は数十年間ほとんど変わりませんでした。現在、進行性の癌やメラノーマの治療アルゴリズムは新しい治療法によって変化しており、同様のアプローチが肉腫の研究分野にも適用されています。サブタイプ特異的な癌生物学における最近の発見と、明確な分子標的の同定により、犬の肉腫治療の状況を変える可能性のある有望な標的戦略が開発されている。この総説の目的は、免疫療法、チェックポイント阻害剤、細胞の代謝を再プログラムできる薬剤など、腫瘍研究で最も活発なパラダイムの多くにまたがる肉腫治療のための新たなアプローチと、現在の標準治療とその限界について説明することである。
犬のメラノサイト腫瘍における腫瘍浸潤リンパ球。CD3+およびCD20+リンパ球集団の予後に対する役割の検討
近年、いくつかの種類の腫瘍における免疫反応の研究が急速に進んでいる。その目的は、腫瘍細胞と免疫細胞の間の相互作用と、がんの病因および進行におけるそれらの重要性を理解すること、およびがん免疫療法の標的を特定することである。メラノーマは、最も免疫原性の高い腫瘍の1つと考えられているにもかかわらず、リンパ球が豊富に浸潤していても進行することがあるため、免疫反応が腫瘍の成長を効率的に制御できていないことが示唆されている。本研究の目的は、97の犬のメラノサイト腫瘍における腫瘍浸潤リンパ球(TIL)の密度、分布、およびグレードが、悪性度の組織学的指標と関連し、犬の予後因子と考えられるかどうかを調査することである。メラノサイト腫瘍における免疫反応の特徴をさらに明らかにするために、免疫組織化学的な調査を行い、TILの2つの主要な集団であるTリンパ球(CD3+)とBリンパ球(CD20+)を評価した。本研究の結果、犬のメラノサイト腫瘍、特に口腔内メラノーマでは、TILが大きな割合で存在し、その浸潤は通常軽度であることがわかった。CD20+ TILの量は、分裂数、細胞の多形性、色素細胞の割合など、いくつかの組織学的な予後因子と有意に関連していた。驚くべきことに、CD20+ TILsの高い浸潤は、腫瘍関連死、転移・再発の存在、全生存期間および無病生存期間の短縮、死亡および再発・転移の発生の危険性の増加と関連しており、犬のメラノサイト腫瘍における新たな予後不良因子となる可能性を示した。
口腔扁平上皮癌の猫に対する加速低分画放射線治療と全身治療の同時併用による毒性と転帰
最近、猫の口腔扁平上皮癌(SCC)に対して、内科的治療と加速放射線治療を組み合わせたマルチモーダルなアプローチが、小規模なパイロット研究で大幅な治療成績の改善を示した。ここでは、切除不能で組織学的に確認された口腔扁平上皮癌で、初期の病期分類が完了した猫51頭をレトロスペクティブに検討した。A群(n = 24)の猫は、ブレオマイシン、ピロキシカム、サリドマイドからなる内科的な血管新生阻害治療を受け、B群(n = 27)の猫は、血管新生阻害治療と同時に48Gyを10回に分けて照射する加速低分割放射線療法を受けた。全体の無増悪期間(PFI)の中央値は70日(95%CI:48;93)と不良であった。しかし、放射線治療を受けた猫(B群)では、PFIが179日(95%CI:58;301)と有意に長く、内科的治療のみの猫では30日(95%CI:23;38)であった(P < 0.001)。全生存期間(OS)の中央値は89日(95% CI: 55;124)で、これも照射した猫(B群)では136日(95% CI: 40;233)対38日(95% CI: 23;54)と有意に長かった(P < .001)。しかし、B群の27頭のうち8頭(29.6%)で重度の毒性(グレード3)が発生した。毒性の発現や重症度は、解剖学的部位、腫瘍の大きさ、臨床病期、ネオアジュバント療法の期間など、試験した変数のいずれとも関連しなかった。化学放射線療法後の重篤な急性症状やQOLへの影響を考えると、患者は治療のリスクについて明確に知らされなければならない。全体的に予後が悪く、急性毒性の発生率が高いことから、猫の口腔内SCCに対して、この加速照射プロトコルと抗血管新生療法の併用を推奨することはできない。
犬のメラノーマに異常に発現したsnoRNA、snRNA、piRNA、tRF
低分子ノンコーディングRNA(sncRNAs/sRNAs)のうち、マイクロRNA(miRNA)の機能制御については、犬の口腔内メラノーマ(COM)で研究されている。しかし、small nucleolar RNA(snoRNA)、small nuclear RNA(snRNA)、transfer RNA-derived fragments(tRF)、PIWI-interacting RNA(piRNA)など、その他のsncRNAのCOMにおける発現レベルは不明である。本研究の目的は、我々が実施しているsmall RNA sequencingプロジェクト(PRJNA516252)から、COMにおけるmiRNA以外のsncRNAを調査することであった。その結果、COMではいくつかのsnRNAとpiRNAが上昇し、tRFとsnoRNAは低下していた。犬のメラノーマ組織と細胞株において、U1 snRNAとpiR-972の発現上昇、tRNA-ser (1)とsnoRA24の発現低下が定量的逆転写PCR法により確認された。同様に、COM症例の血漿中のtRNA-ser (1)とsnoRA24の発現も低下していた。最後に、ヒト表皮メラノサイト細胞(HEMa-Lp)と比較して、ヒト皮膚メラノーマ細胞株(MEWO)では、U1とsnoRA24の発現傾向が同様であることを発見しました。今回の研究では、メラノーマの進行に伴い、snRNA、snoRNA、tRF、piRNAの発現が異常になっていることがわかりました。さらに、メラノーマに関連するU1とsnoRA24の発現は、ヒトとイヌのメラノーマで類似していた。
アドレナリン受容体拮抗薬であるプロプラノロールおよびカルベジロールは、犬の骨肉腫細胞の生存率を低下させ、持続性のあるカルベジロールは、クローン生成生存率を低下させ、放射線感受性を増加させる
アドレナリン受容体(AR)の発現は、原発性および転移性腫瘍のいくつかの部位で確認されており、増殖、生存、転移、血管新生に影響を及ぼす可能性がある。プロプラノロールやカルベジロールなどのARアンタゴニストは、一部の癌において増殖を抑制し、アポトーシスを誘導し、化学療法剤との相乗効果を発揮する。放射線耐性は、多くの細胞で生存促進経路のアップレギュレーションによって媒介されるが、これはARの影響を受けている可能性がある。ARアンタゴニストと放射線の併用を評価した研究は限られている。本研究の目的は、肉腫細胞株の生存率および放射線感受性に対するプロプラノロールおよびカルベジロールの効果を明らかにすることであった。仮説は、プロプラノロールとカルベジロールが4つの初代骨肉腫細胞株の放射線感受性を高めるというものであった。プロプラノロールまたはカルベジロールの単剤投与は、濃度依存的にすべての細胞株の細胞生存率を阻害した。カルベジロールの平均阻害濃度(IC50)は、プロプラノロールよりも約4倍低く、in vivoでの臨床的意義があると考えられた。イムノブロット解析では、ヒトとイヌの肉腫細胞株の両方でARの発現が確認されたが、ベースラインのARタンパク質発現と放射線感受性には相関がなかった。カルベジロールおよびプロプラノロールを短期間投与しても、クローンの生存率には大きな影響はなかった。プロプラノロールおよびカルベジロールの長期投与は、3Gy照射後の犬骨肉腫細胞の生存率を有意に低下させた。今回の結果とイヌにおけるin vivoでの活性の可能性に基づいて、肉腫に対するカルベジロールの効果を調査するためのさらなる研究が必要である。
物議を醸した犬の皮下鞭毛腫瘍の組織学的分類。血管周囲壁腫瘍への道
渦巻き状の成長パターンを特徴とする皮下の紡錘細胞腫はイヌでは一般的であり、独自の存在として認識されている。これらの腫瘍は、ヒトの腫瘍とのわずかな形態上の類似性から、血管周皮腫(HPC)と誤って呼ばれていた。獣医学では、HPCの起源となる細胞について長い間議論されてきた。血管周囲の起源を示唆する著者もいれば、神経周囲の起源を示唆する著者もいる。腫瘍細胞が血管の周りに配向していることや、収縮タンパク質が発現していることから、血管周囲由来が支持されたが、S100の発現や血管の接続が一貫していないことから、神経周囲由来が支持された。ヒトの末梢神経鞘腫瘍と形態的に類似しているにもかかわらず、神経周囲由来は主に特異性の低いマーカーの発現によって支持された。一方、大多数の研究は、「古い」犬のHPCの血管周囲由来を支持している。様々な程度の筋膜-氷結分化が記載されていたため、HPCを置き換えるために血管周囲壁腫瘍(PWT)という用語が提案された。PWTの診断基準が定義されると、臨床的挙動と予後変数が調査され、一般的な犬の軟部組織肉腫(STS)群と比較して違いが示されました。PWTは攻撃性が低く、ほとんどが局所浸潤性であり、転移することは稀である。その挙動は組織学的悪性度の影響をあまり受けないようで、犬のSTSが異質であることを示唆しています。特定のSTS腫瘍タイプの生物学的挙動を研究することは、STSが同時に研究されていたときには気づかなかった差異を検出する上で価値があるかもしれない。