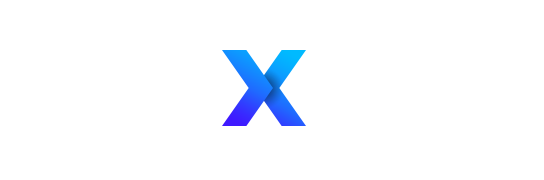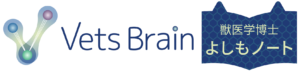肥満細胞腫(MCT)は多くの生物種で報告されており、ヒト、イヌ、ネコの肥満細胞の新生物学には、がん原遺伝子であるKITの変異が関与している。本研究では、肥満細胞の新生物として知られているいくつかの種の間で、KIT遺伝子のヌクレオチドとキットのアミノ酸配列の相同性が高いこと、特にチーター(Acinonyx jubatus)と家猫(Felis catus)のKIT配列の間に高い配列保存性があることを明らかにした。その結果、最近の症例シリーズでMCTと診断された4頭のチーターの新生物DNAにKITの変異が存在するのではないかという仮説を立てた。PCRとサンガーシークエンスにより、4頭のチーターのうち2頭に保存的なエクソン6のKIT変異が確認された。変異の内容は2頭のチーターで異なっていた。残りの2頭のチーターのMCTでは、KITのエクソン6、8、9、11の野生型DNAのみが観察された。飼い猫の皮膚MCT20個を採取し、KITの変異を比較した。12個の腫瘍がKITのエクソン6、8、9のいずれかに変異を有していた(60%、95%CI 38.5%~81.5%)。エクソン11には変異が検出されなかった。家猫のMCTのKIT変異状態と腫瘍の組織学的グレード(従来の模式図、P = 0.934;Sabattini 2層模式図、P = 0.762)または分裂指数(P = 0.750)との間には有意な関連はなかった。KITのmRNAおよびKitタンパク質の配列は種を超えて保存されているが、ネコMCTの病因におけるKITの役割は完全には解明されていない。
好中球対リンパ球比はネコの乳腺癌の独立した予後判定マーカーである
血液中の白血球数とそれに由来する比率は、獣医学におけるいくつかの腫瘍の潜在的な予後マーカーとして記述されている。本研究では、猫の乳腺癌(FMC)の予後因子として、末梢血白血球亜集団および好中球-リンパ球比(NLR)を評価することを目的とした。2017年から2019年にかけてFMCと診断された猫の医療記録をレビューした。猫は、完全にステージングされ、WHOステージI~IIIに分類され、乳房切除術に提出された場合に含まれた。猫は、他の疾患の証拠がある場合は除外した。49匹の猫が対象となった。試験のエンドポイントは,無病期間(DFI)と腫瘍特異的生存期間(TSS)であった。DFIとTSSの中央値はそれぞれ389日と528日であった。単変量解析では、総白血球数(WBC)、好中球数(NEU)、NLRの値が高いことが、両エンドポイントの有意な予後因子として同定された(P < 0.05)。多変量解析では、NLRは依然としてTSSの独立した予後因子であった(P = 0.024)。受信者動作特性曲線解析では、WBCの推定カットオフ値は8.49×109/L(DFIおよびTSS)、NEUの推定カットオフ値は4.62×109/L(DFI)および6.65×109/L(TSS)、NLRの推定カットオフ値は2.46であった。これらのカットオフ値は、DFIおよびTSSにおいて有意な予後因子であった(P < 0.05)。NLRのカットオフ値は、多変量解析においてもDFI(P = 0.032)とTSS(P = 0.043)の独立した予後因子であった。以上の結果から、NLR、NEU、WBCは術前の重要な非侵襲的予後判定マーカーとなりうること、またNLRはFMCの独立した予後判定マーカーであることが示唆された。その臨床的使用を検証するためには、前向きの研究が必要である。
乳腺癌の猫におけるBRCA1およびBRCA2遺伝子の遺伝的変異について
乳腺腫瘍は、女性と猫において、それぞれ1番目と3番目に発生する新生物です。ネコの乳腺腫瘍の約85%は悪性で侵攻性であり、特にトリプルネガティブおよびHER-2+の分子サブタイプである。トリプルネガティブ基底膜様ネコ乳腺がん(FMC)は、ヒトの基底膜様トリプルネガティブ乳がん(TNBC)と臨床的・形態的に類似しているため、適切なモデルと考えられる。女性のTNBCは予後が悪く、腫瘍抑制遺伝子であるBRCA1およびBRCA2の変異と関連していることが多い。そこで本研究では、FMCを発症した9頭のメス猫を対象に、BRCA1とBRCA2の体細胞変異と生殖細胞変異をスクリーニングすることを目的とした。遺伝子解析のために、全血とFMCのサンプルを合わせて採取した。さらに、病理組織学的および免疫組織化学的評価のために、腫瘍のサンプルを追加で入手した。ゲノムDNAを分離し、BRCA1およびBRCA2遺伝子の27のエキソン領域を増幅し、次世代シークエンスでスクリーニングした。BRCA2のエクソン11に機能的影響の高い体細胞変異が1匹のFMC保有猫で4.34%の頻度で見つかった。また、9匹のFMC保有猫のうち3匹で、BRCA1のエクソン9に限定して、中程度の影響を持つ4つの生殖細胞変異体が検出されました。以上より、FMC保有動物の3分の1に見られる生殖細胞系列の遺伝子変異は、遺伝性の乳腺発がんのリスクを高める可能性があると結論づけられた。
自然発生した頭頸部癌の飼い猫における低侵襲のエチルセルロース・エタノール・アブレーション。6匹の猫
大きな腫瘍やカプセル化されていない腫瘍では、中毒を起こしたり周辺組織を損傷したりすることなく、致死量のエタノールを保持することは困難である。エチルセルロース-エタノールアブレーション(ECEA)は、エタノールを腫瘍内に封じ込めることで、この制限を克服している。ECEAの安全性を評価し,臨床的に実現可能なワークフローを開発するため,舌/舌下扁平上皮癌(SCC)の猫を対象とした単群パイロット試験を実施した.6匹の猫に、エタノールに溶解した6%エチルセルロースの腫瘍内注射を行った。被験者は一晩観察された。軽度の出血と一過性の体温上昇、注射部位の痛みと腫れが見られたが、抗炎症薬で改善した。血清エタノールの上昇はわずかで、平均濃度は注射の1時間後にピークに達した(129±15.1nM)。猫は1週目と2週目に再検査を受けた。QOLが安定し、治療に部分的に反応した猫(n=3)にはブースター治療が行われた。その後、月1回のペースで再検診を行った。各動物において最長の腫瘍寸法が増加した(cRECISTによる進行性疾患)が、ECEA後1週間以内に、6頭中3頭において推定腫瘍体積が減少した。すべての猫は安楽死させられた(生存期間中央値70日)。その理由は、局所的な腫瘍の進行および/またはECEAによって早まったと思われる舌の機能障害であった。ECEAは猫の舌側/舌下SCCに対する実行可能な治療法ではない。一部の猫では腫瘍量を効果的に減少させることができたが、同時に舌の機能が失われたために忍容性が低かったのである。さらなる最適化により、ECEAは猫の他の口腔部位のSCC、および他の種の頭頸部悪性腫瘍に有用な選択肢となるかもしれない。
犬の乳腺腫瘍におけるTRPM7の発現と予後判定
犬の乳腺腫瘍(CMT)は、無傷の雌犬に最もよく見られる腫瘍の一つである。犬の乳腺を対象とした以前の研究では、健康な犬の乳腺組織にTRPM7(transient receptor potential melastatin 7)イオンチャネルが存在することが示された。しかし、CMTにおけるTRPM7の意義はまだわかっていない。TRPM7は、プロテインキナーゼドメインを含むCa2+およびMg2+透過性のカチオンチャネルである。本研究の目的は,イヌの良性および悪性のCMT組織57例におけるTRPM7の発現を免疫組織化学(IHC)を用いて決定し,臨床病理学的特徴との相関を評価するとともに,前向きな生存研究においてTRPM7の潜在的な予後的価値を探ることであった。IHC解析の結果、TRPM7は新生物の上皮細胞の細胞質に発現していた。さらに、TRPM7の発現は、腫瘍の悪性度(P = 0.027)、Ki-67指数(P < 0.0001)および転移(P < 0.0001)と有意に関連していました。生存曲線解析では、TRPM7の高発現は、悪性CMTにおける無病生存率(P = 0.035)および全生存率(P = 0.011)の低下と有意に関連していた。今回の結果から、TRPM7はCMTsで発現しており、その発現は臨床病理学的パラメータと正の相関があることが明らかになった。したがって、TRPM7はCMTsの潜在的な予後因子であると想定された。
DNAメチル化およびTP53変異解析によるネコの口腔扁平上皮癌の同定のための非侵襲的手法としての口腔ブラッシングの検証
猫の口腔扁平上皮癌(FOSCC)は、頻度が高く、進行性の浸潤性腫瘍である。初期の病変は、唯一の臨床検査に基づいて認識することが難しく、非腫瘍と誤認されることがある。FOSCCでは、TP53の変異や特定の遺伝子のエピジェネティックな変化が見られ、早期に発見できる可能性がある。この前向き研究の目的は、口腔ブラッシングによって得られたFOSCCの細胞サンプルについて、17遺伝子パネルのDNAメチル化パターンとTP53変異の状態を調べることである。結果は、FOSCCのスクリーニングのためのこの非侵襲的な手順を検証するために、対照群と比較した。FOSCCでは、対応する組織学的サンプルがある場合には、同じ分析を行った。35名のFOSCCと60名の対照群が含まれた。TP53の変異は、FOSCCのブラッシングでは17個(48%)、対照では1個も検出されなかった(P < 0.001)。FOSCCでは6つの遺伝子(ZAP70、FLI1、MiR124-1、KIF1A、MAGEC2、MiR363)のメチル化が異なっており、メチル化スコアに含めた。TP53の変異状態とメチル化スコアに基づいたアルゴリズムにより、FOSCCと対照群を69%の感度と97%の特異度で区別することができた(精度は86%)。19例のFOSCCの組織標本では、TP53の変異状態はブラッシングと完全に一致し、メチル化スコアは全例で陽性であった。これらの結果は,口腔内ブラッシングによるFOSCCの同定に有望であるが,いくつかの要因がこの手法の精度を制限している可能性があり,臨床現場での再現性を評価するためのさらなる研究が必要である.
口腔内悪性黒色腫の犬における初回治療としての治癒目的 vs 辺縁切除の転帰の違いと、アジュバントCSPG4-DNAエレクトロワクチンの影響。155例を対象としたレトロスペクティブ研究
犬の口腔内悪性黒色腫は、局所浸潤性で転移性が高い。現在のところ、局所制御のための最良の選択肢は、一括切除後、切除断端が不完全な場合は放射線照射を行うことである。補助療法としての化学療法の役割は疑問視されているが、免疫療法は有望である。このレトロスペクティブ研究では、単一施設で管理された155頭の口腔内悪性黒色腫(I期24頭、II期54頭、III期66頭、IV期11頭)を評価した。目的は、発症時に治癒目的で外科的治療を受けた犬(第1群)と、わずかに切除しただけの犬(第2群)の間で、生存期間(MST)および無病期間(DFI)の中央値の違いを評価することであった。MSTは、第1群の方が第2群よりも長かったが(594日対458日)、有意差は認められなかった(P=0.57)。しかし、DFIについては統計的な差が認められた(232日対183日、P=0.008)。ワクチン接種を受けた犬のサブ集団において、アジュバントである抗CSPG4 DNA電気泳動の影響を評価したところ(治癒目的、第3群、対限界、第4群)、MST(1333日対470日、それぞれP = 0.03)とDFI(324日対184日、それぞれP = 0.008)の両方で有意差が認められた。進行性疾患は、全体(P=0.03)とワクチン接種犬(P=0.02)の両方で、治癒目的の切除よりも限界切除を受けた犬に有意に多く見られた。本研究では、犬の口腔内悪性黒色腫に対して、病期分類後、広範囲切除とアジュバント免疫療法の併用が有効なアプローチであることが指摘された。
JARID1を標的としたヒストンH3デメチラーゼ阻害剤は、犬の口腔内メラノーマ細胞株において、抗増殖活性を示し、シスプラチン耐性を克服する。
多くのがんにおいて、ヒストンデメチル化酵素は過剰に発現したり、活性が変化したりして、細胞周期やDNA修復の動態を変化させ、治療抵抗性を引き起こす。そのため、ヒストンデメチラーゼを標的とした治療法は、ヒトの腫瘍学において活発で有望な研究分野となっている。しかし、犬のがんにおけるヒストンデメチラーゼの役割とデメチラーゼ阻害の効果については、ほとんど知られていない。本研究では、犬の口腔内メラノーマにおけるヒストンデメチラーゼ阻害剤(HDI)の治療効果を調べることで、この知識のギャップを解消した。犬のメラノーマ細胞株を用いて、広義のHDIは細胞生存率を低下させ、DNA損傷修復動態を延長させることを明らかにした。さらに、ヒトの癌において増殖-休止の制御や薬剤感受性に関与するヒストンH3デメチラーゼであるJARID1Bが、犬の腫瘍組織で高発現していることを示しました。JARID1Bおよび関連するJARID1ファミリーを標的としたHDIは、犬のメラノーマ細胞株の生存率を有意に低下させたが、広範囲のHDI治療のようなDNA損傷修復動態の変化は見られなかった。重要なことは、JARID1を標的としたHDIの抗増殖効果が、プラチナ系化学療法に耐性を持つ細胞株においても維持されることを発見したことであり、従来の治療法を用いても進行する口腔内メラノーマに直面した場合、HDIが有効な治療戦略となる可能性が示唆された。