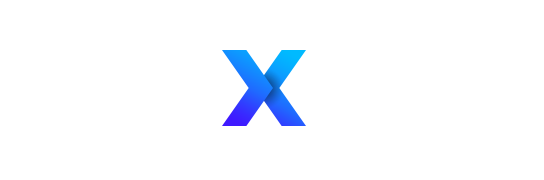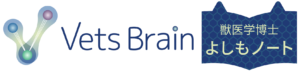メルケル細胞癌(MCC)は、ヒトとネコでは悪性の皮膚神経内分泌癌であるが、イヌではより良性の挙動を示す可能性があるとされている。細胞形態学的に顕著な類似性があるため、リンパ腫などの円形細胞腫と混同されることがある。MCCはメルケル細胞から発生すると考えられているが、最近の知見では、原始的な(表皮)皮膚幹細胞、初期のB細胞または皮膚線維芽細胞がヒトMCCの起源であることが示唆されている。本研究の目的は、ネコとイヌのMCCにおけるリンパ系由来の可能性を評価することである。3匹のネコと3匹のイヌのMCCにおいて、CD3、PAX-5、KITおよびPARRアッセイの特異的分析を行った。すべてのMCC(6/6)はCD3とPAX-5が陰性であった。KITはすべてのMCC(6/6)で発現していた。PARRアッセイによるクローン性の評価では、テストした5例すべてにおいて、ポリクローナルなB細胞およびT細胞受容体の再配列が認められた。結論として、ネコとイヌのMCCのリンパ系起源は証明されなかった。このことは、ヒトのMCCがしばしば初期のB細胞系マーカーを発現しているのと対照的である。
102頭の犬の皮膚血管周囲壁腫瘍における臨床、血液学、病理組織学的変数の予後への影響
血管周囲壁腫瘍(PWT)の予後因子の同定は、予後を正確に予測し、治療の指針とするために望ましい。この多施設共同研究では、遠隔転移のないPWTを外科的に切除した100頭と2頭の犬をレトロスペクティブに登録し、治療前の白血球パラメータ、臨床的および病理組織学的変数が局所再発(LR)および全生存期間(OST)に及ぼす影響を評価した。白血球数(WBCC)、好中球数(NC)、好中球-リンパ球比(NLR)の増加は、単変量解析でLRのハザードと有意に相関した。WBCCとNCは、断端、悪性度、腫瘍の大きさ、位置、皮膚潰瘍で調整しても予後を左右したが、有糸分裂指数と壊死で調整すると有意性を失った。一方、NLRは、断端が浸潤していると分類された場合にのみ予後を左右した。単変量解析では、去勢された男性の方が無傷の男性よりもLRのハザードが高かったが、多変量モデルでは有意性が失われた。潰瘍化したPWTと遠位四肢に位置するPWTは、単変量解析と多変量解析の両方でLRのハザードが高かった。組織学的グレード、壊死、有糸分裂数、浸潤した辺縁はすべて、単変量解析と多変量解析の両方でLRと関連していた。Boxerの品種、高齢、潰瘍、グレードIII、壊死度50%以上、有糸分裂数の多さは、OSTの短さと相関していたが、品種と年齢は多変量解析では有意性を失った。外科的に切除されたPWTの予後は、臨床的変数と病理組織学的変数の両方に基づいて判断すべきである。さらなる研究で検証されれば、白血球数とNLRは臨床家が治療前にLRのリスクが高い犬を特定するのに役立つだろう。
123頭の犬に定位体放射線治療を行った犬の虫垂型骨肉腫の治療成績と予後
「犬の虫垂骨肉腫は一般的に四肢切断で治療されるが,一部の患者では四肢温存の選択肢が頻繁に望まれたり必要とされたりする。我々は、定位体放射線療法(SBRT)で治療した123例、130部位を評価した。98頭中82頭(84%)が、中央値3週間、中央値6ヶ月で最大の跛行の改善を示した。切断や剖検で得られたサンプルを病理組織学的に評価したところ、50%の四肢で80%以上の腫瘍壊死が認められ、局所病変のコントロールが確認された。評価可能な患者のうち、41%が治療後に骨折し、21%が切断を余儀なくされた。細針吸引(n=52)と針生検(n=28)では、腫瘍を採取しなかった場合(n=50)に比べて、骨折のリスクは増加しなかった。生存期間(MST)の中央値は233日、初回イベントまでの期間は143日であった。腫瘍の総体積と計画された標的体積は生存期間と有意に逆相関し,腫瘍の位置は生存期間と有意に相関した.サルベージ切断を行った犬は、行わなかった犬に比べてMSTが有意に長かった(346日対202日、P = 0.04)。15頭の犬で治療時に転移があっても、生存期間に有意な影響はなかった(転移がない場合の200日対237日、P = 0.58)。皮膚の副作用は投与量と有意な相関があり、急性のグレード3の影響を受けた患者の33%が結果的に後期のグレード3の影響を受けた。SBRTはほとんどの患者で跛行を改善するが、治療を開始する前に初期の骨折リスクを最小限に抑える候補者を特定するには、さらなる調査が必要である。
犬の皮下の軟部組織肉腫を覆う皮膚の腫瘍性浸潤の評価。探索的研究
犬の皮下軟部組織肉腫(sSTS)を覆う皮膚への腫瘍の浸潤に関する研究は不足している。腫瘍が浸潤していない場合には、この患部のない皮膚をそのままにしておくことで、手術を簡略化できる可能性がある。本研究の目的は、sSTSの上にある皮膚に腫瘍細胞が浸潤しているかどうかを調べることである。外科的治療を受けたsSTSの犬が前向きに登録された。切除後、皮膚は自然な外科的切断面に沿って腫瘍から切り離され、組織学的に評価された。sSTSを有する29頭の犬が対象となった(グレードIが22頭、グレードIIが6頭、グレードIIIが1頭)。sSTSを覆う皮膚は14/29例(48.3%)で腫瘍の浸潤を認めなかった。浸潤の頻度は、グレードの高いsSTS(グレードIIおよびIII、100%;P = 0.006)で観察された。それにもかかわらず、8/22例のグレードIのsSTS(36%)では、皮膚への浸潤も認められた。この浸潤は、腫瘍に直接触れている皮膚の真皮にまで及んでいた(11例は多房性、4例はびまん性)。グレードIのsSTSでは皮膚への腫瘍浸潤の頻度は低く、局所制御の可能性を高めるためには、どのsSTSでも広い範囲を切除することが最も安全な治療法であると考えられるが、本研究では、sSTSに直接接触している皮膚のみが腫瘍浸潤していることが証明されたため、より積極的ではないが局所治癒を目的とした皮膚切除の可能性を示している。特に低悪性度のsSTSでは、この皮膚のみの切除が完全な局所制御を保証することを確認するために、さらなる研究が必要である。
犬・猫における治験治療後の有害事象に関する獣医学的協同腫瘍学グループ-共通用語基準(VCOG-CTCAE v2)について
更新されたVCOG-CTCAE v2ガイドラインには、前回の更新版(v1.1)が2011年にリリースされ、2016年に「Veterinary and Comparative Oncology」内で発表されて以来、いくつかの重要な更新と追加が含まれています。Veterinary Cooperative Oncology Group(VCOG)はもはや活動していないため、VCOG-CTCAE v1.0およびv1.1の原著者および貢献者に意見を求め、有害事象(AE)カテゴリーの拡大および改良のために追加の共同執筆者を求めた。VCOG-CTCAE v2では、神経系、心臓系、免疫系のAE項目が拡充されたほか、手技特有のAEが追加された。ACVIM のサブスペシャリティと American College of Veterinary Surgery から追加の著者を迎え入れることで、様々な病態、臨床シナリオ、身体システムで実施された臨床試験で観察された AE をより包括的に捉えることができると考えています。また、この更新された獣医学CTCAEガイドラインが、一般的な獣医学的診療や、様々な疾患を持つ動物の新しい治療戦略を評価する臨床試験において、より良い適用と使いやすさを提供することを目的としています。今回の改訂作業では、各AEカテゴリーのグレーディング構造が、用量制限事象の決定に適用される意思決定プロセスを反映したものになるように努めました。第Ⅰ相試験の決定はこれらの基準に基づいて行われ、最終的には最大耐量が決定されるため、 新薬の登録や申請の際の標準的な投与量の推奨に影響を与えることになる。この文書は定期的に更新し、獣医の患者を対象とした臨床試験への継続的な適用を反映させるべきである。
犬骨肉腫細胞株に対して生物学的活性を示す選択的核外排出抑制剤(SINE)ベルディネクサー
Verdinexor(KPT-335)は、経口投与可能な新規の選択的核外排出抑制剤(SINE)であり、核外排出タンパク質であるExportin 1(XPO1/CRM1)の機能を阻害する。本研究では、犬の骨肉腫(OS)の初代腫瘍サンプル、OS細胞株および正常骨芽細胞におけるXPO1の発現の特徴を明らかにし、verdinexorの単独またはドキソルビシンとの併用によるin vitro活性を評価することを目的としました。犬のOS細胞株および初代OS腫瘍のサブセットでは、正常な犬の骨芽細胞と比較して、XPO1の転写産物およびタンパク質の発現が増加していた。すべての犬のOS細胞株は、低ナノモル濃度のベルディネキソールに反応して、用量依存的な増殖抑制とカスパーゼ3,7活性の上昇を示した(IC50濃度は21~74nM)。注目すべきは、ベルディネクサーで処理した正常な犬骨芽細胞細胞株の成長阻害は、高マイクロモル濃度で観察されたことである(IC50=21μM)。Verdinexorとdoxorubicinの併用は、3つのイヌ骨芽細胞株において強力な細胞生存率の阻害をもたらし、相乗効果を発揮した。同時に、OS細胞株では、ドキソルビシンで処理した後、24時間通常の培地で回復させた細胞と比較して、ヴェルディネクサーで処理した後、γH2A.Xの病巣が増加した。これらの結果から、Verdinexorは犬のOS細胞株に対して生理学的に適切な用量で生物学的活性を有することが示され、XPO1の阻害と標準的なドキソルビシン治療との併用は、犬のOSにおける化学療法介入の有望な可能性を示唆している。
手術およびCSPG4抗原電気泳動の補助療法を受けた口腔内悪性黒色腫の犬における治療前の好中球/リンパ球比およびリンパ球/単球比が予後に与える影響の評価:探索的研究
癌の進行における全身性炎症の役割は、特にヒトのメラノーマにおいて広く研究されている。治療前の白血球数と比率は、いくつかの種類の悪性腫瘍において予後に影響することが認められているが、犬の口腔内悪性黒色腫(COMM)に関しては情報がない。この探索的なレトロスペクティブ研究の目的は、外科的切除およびアジュバントCSPG4抗原電気泳動による免疫療法を受けた口腔悪性黒色腫の犬において、治療前の好中球/リンパ球(NLR)およびリンパ球/単球(LMR)比が予後に与える影響を調べることである。組織学的に口腔内悪性黒色腫が確認され、初回治療の最大60日前に行われた治療前の血液学的分析が可能な39頭の犬をレトロスペクティブに登録した。NLRおよびLMRと、年齢、臨床病期、腫瘍の色素沈着、腫瘍の大きさ、核異型度、分裂指数、Ki67、CSPG4の発現、潰瘍形成、骨浸潤、切除断端の状態との間に考えられる相関関係を探るため、統計解析を行った。NLRとLMRが全生存期間(OST)に与える影響について、様々な比率のカットオフ値と異なる時点でのKaplan-Meier法を用いて検討した。白血球比率と組織学的パラメータ、CSPG4の発現、切除断端の状態、年齢、腫瘍の大きさ、臨床病期との間に有意な関係は認められなかった。NLRとLMRは、全集団の生存期間に予後的な影響を示さなかった。治療前の白血球比率は、口腔内メラノーマの犬において、特に遠隔転移がない場合には、有用な予後因子とはならない可能性がある。
6頭の犬の喉頭全摘出と永久気管切開術
この報告の目的は、6頭の犬における喉頭全摘出の手術手技とその結果について述べることである。喉頭癌は珍しく、難しい臨床問題である。喉頭全摘術は局所的な病変のコントロールが可能であるが、実施されることは稀である。詳細な手順の記述は限られており、同様に患者の転帰に関する情報も限られている。喉頭全摘術を受けた犬について、施設の医療記録を検索した。6頭の犬が確認された。この手術は永久気管切開のみの場合と同様の術後のQOLをもたらした。外科的マージンの状態は6例中5例で評価され、その5例では完全であった。すべての犬は退院まで生存した。合併症はほとんどが永久気管切開に伴う合併症として認識されている気管切開部の閉塞や崩壊に関連していた。患者のQOLは問題なかった。1頭の犬で局所再発が疑われた。縁の状態が不明の症例では再発は認められなかった。
犬の前立腺癌および尿路上皮癌の細胞学的検出に関する病理医のレビュープロトコルの比較。298例を対象とした2施設合同のレトロスペクティブ研究
尿路上皮癌は、移行細胞癌としても知られており、犬の最も一般的な原発性膀胱腫瘍であり、前立腺を侵すこともあります。細胞診は、膀胱や前立腺に病変のある犬によく用いられる診断ツールである。このレトロスペクティブな研究の目的は、尿路上皮癌または前立腺癌に対する細胞学的評価の感度と特異性を、細胞学的審査プロトコルの異なる2つの施設間で比較すること、および特定の採取方法が細胞学的精度を高めるかどうかを判断することである。合計298例が対象基準を満たした。全体の感度と特異度は、第1施設ではそれぞれ91.8%と50%であったのに対し、第2施設ではそれぞれ31.1%と97.4%であった。施設2の尿サンプルレビュープロトコルを施設1のものと一致させた場合、感度と特異度はより施設1に近かった(それぞれ71.2%、88.9%)。この結果から、細胞診の感度と特異度は、異なる施設で実施されているスクリーニングとレビューのプロトコルによって影響を受けることがわかりました。また、感度と特異度が採取方法によって異なることも示された。診断用カテーテル検査が最も高い性能を示した。2施設間の11例のうち、感度と特異度は100%であった。一方、診断用カテーテルで採取していない尿沈渣の検査は、感度・特異度ともに低く、施設によって大きく異なっていた。以上のことから、細胞診を行う際には、処理方法と採取方法の両方を考慮する必要がある。