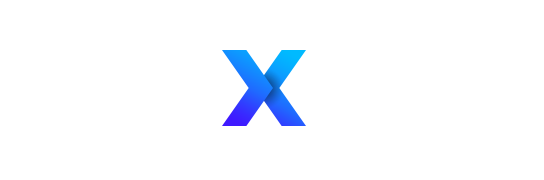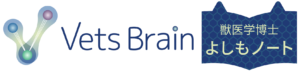ヒトの場合、B症状とは、発熱、体重減少、寝汗などのリンパ腫の全身症状を指し、患者の予後に影響する。犬のリンパ腫では、サブステージBは観察されたすべての臨床症状を表すために使用される。このレトロスペクティブな研究の目的は、犬の結節性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫における治療効果と生存率を予測するために、サブステージBとB症状を比較することである。2008年から2019年にCHOP化学療法を受けた罹患犬を対象とした。B症状は、正常体重の10%以上の体重減少、発熱、人の寝汗に代わる原因不明の安静時頻脈の発生と定義した。サブステージBは、リンパ節腫脹以外の症状と定義した。55例が対象となった。B症状は20/55(36%)、サブステージBは40/55(74%)の患者に認められた。B症状やサブステージBと、体重、性別、犬種、WHOステージ、リンパ腫のグレードとの間には、有意な関連は認められなかった。治療効果は、サブステージB(P = 0.02)とB症状(P = 0.001)の両方と負の関係にあった。B症状は、無増悪生存期間(PFS)(95 vs 330日、P = 0.001)およびリンパ腫特異的生存期間(LSS)(160 vs 462日、P = 0.001)を有意に減少させた。犬の結節性びまん性大細胞型B細胞リンパ腫において、B症状はサブステージBよりも信頼性の高い予後指標である可能性を示すデータであった。より多くの患者で、また他の一般的なリンパ腫でB症状を評価する前向きの研究が必要である。この抄録は、2019年6月22日にルガーノで開催された欧州犬リンパ腫ネットワークグループの第4回会合で発表され、26ページの会合のプロシーディングに掲載された。
乳腺癌の猫に対する補助的なドキソルビシン対メトロノミックなシクロホスファミドとメロキシカム対手術単独。137例のレトロスペクティブ研究
本研究は、乳腺癌の猫を対象に、補助療法として低用量シクロホスファミド化学療法+メロキシカムを、高用量ドキソルビシンや手術単独と比較して、その有効性と副作用を評価することを目的としています。2008年から2018年にかけて乳腺がんの治療を受けた雌猫228頭の医療記録を、8つの動物病院でレビューしました。腫瘍のステージングが完了し、根治的乳房切除術を受けた猫のみが研究対象となりました。137頭の猫を、手術を行った第1群(n=80)、手術とドキソルビシンによるアジュバント治療を行った第2群(n=34)、手術と低用量メトロノミックシクロホスファミドとメロキシカムによるアジュバント治療を行った第3群(n=23)の3つの治療群に分けました。試験のエンドポイントはdisease free interval(DFI)とoverall survival(OS)であった。毒性はVCOG-CTCAE基準に基づいて評価した。DFIの中央値は、1群、2群、3群でそれぞれ270日、226日、372日であった。OSの中央値は338日(1群)、421日(2群)、430日(3群)であった。グループ間の差は有意ではなかった(DFI P=0.280、OS P=0.186)。毒性は、第2群の52.9%(n=18)および第3群の39.1%(n=9)の猫に認められ、軽度から中等度の強度であった。その差は有意ではありませんでした(P = 0.306)。結論として、アジュバント化学療法による治療は生存率を向上させず、全体的な有益性はまだ証明されていません。猫の乳腺癌に対するアジュバント化学療法治療の有効性を明らかにするためには、無作為化プロスペクティブ試験が必要である。
イヌのアンドロゲン受容体のN末端に存在するグルタミンの数がシグナル強度に影響を与える
ほとんどの雄犬は若くして去勢されているため、アンドロゲン除去後の飼育が容易である。犬の前立腺がんの発生率は低いが、何人かの患者はアンドロゲン療法に抵抗を示し、臨床予後も悪い。これらの結果は、末期のヒトのアンドロゲン非依存性前立腺がんの結果と似ている。イヌのアンドロゲン受容体(AR)は、そのN末端に2つのポリグルタミン(polyQ)配列(Q×10とQ×23)を持つ。ポリQの長さはイヌの前立腺がん発症の危険因子であると考えられるが、それを裏付ける証拠はない。そこで、犬のARのpolyQ欠失変異体を人工的に作製し、ARのシグナル伝達に与える影響を評価した。その結果、Q×10とQ×23の欠失は、ARシグナルの強度を著しく低下させた。Q×10変異体は、Qを順次増加または減少させることで、ARシグナルにも変化を与えた。さらに、Q × 10を欠いた変異体は、Q × 10コントロールと比較して、リガンド結合ドメインを含むARのC末端へのpolyQの結合強度が変化したが、これはQ × 9、11、12変異体では観察されなかった。犬のARのN末端に含まれるグルタミンの数は、ARのシグナル伝達強度に影響を与え、犬の前立腺がんのリスクに寄与している可能性がある。
コンパニオンラットの良性乳腺腫瘍におけるプロラクチンおよびアンドロゲン受容体の発現変化
良性乳腺腫瘍は、コンパニオンラット(Rattus norvegicus domestica)の最も一般的な腫瘍の一つであると同時に、動物福祉上の大きな問題であり、安楽死の問題でもある。本研究の第一の目的は、腫瘍化した乳腺組織と正常な乳腺組織におけるエストロゲン、プロゲステロン、アンドロゲン、プロラクチンの各受容体の発現を評価し、これらの受容体の発現を群間で比較することであった。第2の目的は、新生物の乳腺組織におけるこれらの受容体の発現が、全生存率および最初の乳腺腫瘤切除後の追加腫瘤の発生と相関するかどうかを調べることである。第3の目的は、エストロゲン、プロゲステロン、アンドロゲンおよびプロラクチン受容体の発現が、乳腺腫瘍の臨床パラメータや動物の年齢と関連するかどうかを調べることであった。コンパニオンラットから32個の良性乳腺腫瘍を採取し、プロラクチン受容体、エストロゲン受容体α(ERa)、プロゲステロン受容体、アンドロゲン受容体(AR)の免疫組織化学染色に供した。乳腺腫瘍(n=32)とその周囲の正常乳腺組織(n=20)が存在する場合は、Allredスコアを取得した。プロラクチン受容体の発現は乳腺の腫瘍化に伴い有意に増加し(P < 0.0001)、ARの発現は腫瘍化に伴い減少した(P < 0.0001)。腫瘍間質におけるERaの発現低下は、生存期間の短縮と関連していた(P = 0.02)。ホルモン受容体の発現は、年齢、腫瘤径、部位、および追加の腫瘤発生の可能性とは有意に関連しなかった。さらなる研究では、良性乳腺腫瘍のコンパニオンラットを対象としたプロスペクティブな研究で、プロラクチン拮抗薬の効果を調査する必要がある。
猫の注射部位肉腫におけるホルモン受容体の発現、臨床および病理組織学的解析
猫の注射部位肉腫(FISS)は侵攻性で、再発率が高く、まれに転移することがある。この研究の目的は、FISSにおけるエストロゲン(ER)とプロゲステロン(PR)の受容体の発現を免疫組織化学的に評価し、臨床的および病理学的側面と相関させることである。本研究は、FISSの51例を対象としたレトロスペクティブな研究である。免疫組織化学を行い、ビメンチン、ER、PR、Ki67の発現を検出した。臨床的、病理組織学的、免疫組織化学的特徴を予測変数とし、ERとPRの発現を従属変数とした。51例のFISSのうち28例(55%)が女性、23例(45%)が男性で、年齢は10.7±4.2歳、腫瘍の大きさの中央値は3cm(2.0~5.4)であった。患部は体幹が最も多く、38例(84%)であった。組織学的グレードは、分化スコア、壊死、分裂指数を考慮すると、57%の症例でIII度が認められた。ERの発現は64%の症例で陽性であり、有糸分裂指数(P = 0.05)および多形性の程度(P = 0.04)と関連していた。PRはこれらの変数とは関連せず、63%の症例がこの受容体に対して陰性であった。このように、ERの発現は腫瘍の成長に影響を与える可能性がある。FISSのホルモン発現に関する知識は、病態生理学的なメカニズムを明らかにするために重要である。FISSの予後におけるER発現の価値を予測するには、さらなる研究が必要である。
犬の虫垂状骨肉腫におけるテロメアの代替的な長さに関連するCサークルの有病率と潜在的な予後の価値
Alternative lengthening of telomeres(ALT)は、テロメラーゼに依存しないテロメア維持機構(TMM)であり、ヒトの骨肉腫では高い頻度で見られるが、犬の骨肉腫ではまだ知られていない。本研究の目的は、自然発生した虫垂骨肉腫のイヌ患者において、テロメアDNAの染色体外サークルの検出によりALTの有病率を評価し、臨床転帰を評価することである。本研究では、病理組織学的に骨肉腫が確認された50頭の犬を対象とした。医療記録は、患者の特徴、腫瘍学的治療、生存率についてレトロスペクティブに分析された。保存されているFFPE腫瘍組織標本からDNAを分離し、放射性標識プローブを用いてC-およびG-サークルアッセイ(CCAおよびGCA)とテロメリックコンテンツ(TC)の測定に適用した。CCAでは、50例中10例(20%)にALT活性が検出された。投入DNAが1ng以下でも4例のCCA陽性例が検出され、犬の腫瘍に対するCCAの感度の高さが示された。GサークルとTCは、CCA陽性例と陰性例を区別するのに適していなかった。CCA-statusは、男性の性別とロットワイラーの品種との関連を示した。CCA陽性の犬の骨肉腫は、CCA腫瘍の患者よりも全生存期間が短く、CCA-statusはCox比例ハザードモデルにおいて治療法以外の有意な予後因子であった。これらの所見から、犬の骨肉腫はTMMの比較研究のための興味深いモデルであるが、CCA-statusが新たな予後マーカーとして機能するかどうかを調査するために、今後の研究が必要である。
犬のがんにおける血漿25-ヒドロキシビタミンDと炎症反応犬のがんにおける血漿25-ヒドロキシビタミンDと炎症反応
犬のがんでは、循環している25-ヒドロキシビタミンD(25[OH]D)の減少と炎症マーカー濃度の上昇が別々に報告されている。この2つの相関関係はヒトでは存在するが、イヌでの関連性を調べた研究はほとんどない。本研究では、健康な犬とがんの犬の血漿25(OH)Dと炎症性マーカー濃度を測定し、それぞれのグループにおける相関関係を評価することを目的とした。三次腫瘍センターに来院したB細胞リンパ腫(B-cell、n = 25)、T細胞リンパ腫(T-cell、n = 9)、骨肉腫(OSA、n = 21)、肥満細胞腫(MCT、n = 26)と新たに診断された犬と、健康な犬(n = 25)を登録した。血漿サンプルは、25(OH)D、C反応性タンパク質(CRP)、ハプトグロビン(HP)、血清アミロイドA(SAA)、α-1-酸糖タンパク質(AAG)、および13種類のケモカインとサイトカインについて分析された。B細胞を持つ犬は、健康な犬と比較して、血漿25(OH)Dが減少し(P = 0.03)、血漿CRP、AAG、HP、KC-like、MCP-1の濃度が増加した(それぞれP < =.001、.011、<.001、.013、.009)。血漿中のCRP、HP、SAA濃度は、健常犬と比較してOSAの犬で上昇していた(それぞれP = .001、.010、.027)。T細胞とMCTを持つ犬では差が見られなかった。血漿25(OH)D濃度とAAG濃度の間には負の相関関係が認められた。血漿中の25(OH)D濃度と以下の項目との間に負の相関が認められた:T細胞を持つ犬のAAG濃度(Rs=-0.817、P=0.007)、OSAを持つ犬のGM-CSF濃度(Rs=-0.569、P=0.007)、OSAを持つ犬のIL-7濃度(Rs=-0.548、P=0.010)。B細胞患者では、25(OH)D濃度の低下と複数の炎症マーカーの濃度上昇が観察され、25(OH)Dと炎症の関連性が支持された。横断的な研究デザインであったため、変化の時期を特定することはできなかった。前向きなコホート研究が必要である。
犬の新生物細胞の増殖およびオートファジーとアポトーシス中のマイトジェン活性化プロテインキナーゼ活性化に対するカンナビジオールの効果
低テトラヒドロカンナビノールのカンナビスサティバ製品(ヘンプ製品としても知られる)が広く出回るようになり、獣医患者への使用がますます盛んになってきた。使用が一般化しているにもかかわらず、獣医学の文献にはカンナビノイドの有効性に関する証拠に基づいた資料が不足している。大麻に含まれる最も一般的なカンナビノイドはカンナビジオール酸(CBDA)であり、熱抽出の際にカンナビジオール(CBD)となる。CBDは単独および標準的な癌治療との併用による直接的な抗腫瘍効果について研究されており、有望な結果が得られている。本研究の目的は、犬の癌細胞株をCBD単独および一般的な化学療法剤と併用してin vitroで処理した場合の抗増殖および細胞死反応を調べることと、CBDによる処理の反応に潜在的に関与する主要な増殖経路(p38、JNK、AKT、mTORなど)を調べることである。CBDは、2.5~10μg/mLの濃度で処理された5つの犬の新生物細胞株において、CBDAよりもはるかに優れた方法で犬の癌細胞の増殖を著しく抑制した。CBDとビンクリスチンの併用療法は、抗増殖濃度において相乗的または相加的に細胞増殖を抑制したが、ドキソルビシンとCBDの併用療法では明確な結果が得られなかった。また、CBDの細胞内シグナル作用を調べたところ、アポトーシスの誘導に続いてオートファジーが起こることがわかり、オートファジーに先立ってERKとJNKのリン酸化が速やかに起こることが関係していると考えられる。結論として、CBDは細胞の増殖を阻害し、自食作用とアポトーシスを迅速に誘導する効果があり、その有効性と従来の化学療法との相互作用を理解するためには、さらなる臨床試験が必要である。
CHOPプロトコルで治療された犬のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫における予後因子としての末梢血血球比率
びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)は、イヌに最も多く見られる造血器腫瘍であり、ヒトのリンパ腫の臨床モデルとして認識されている。近年、好中球対リンパ球(NLR)とリンパ球対単球(LMR)の比率が、CHOP療法を受けたイヌのDLBCLにおけるtime-to-progression(TTP)とリンパ腫特異的生存(LSS)を予測することが示されている。我々は、DLBCLと診断された59頭の犬を対象に、血液学的パラメータとその比率の予後をレトロスペクティブに評価した。NLR、LMR、血小板リンパ球比(PLR)および血小板好中球比(PNR)は、TTP、LSS、および関連する副次的評価項目(time-to-progression-rate[TTPR]およびlymphoma-specific survival-rate[LSSR])に対する180日および365日後の率として評価した。PNRはTTPR/180日および365日の独立した予後マーカー(p≦0.001)であり、PNRが0.032以上の犬は180日以前に進行する可能性が高かった(感度46.5%、特異度87.5%、p=0.004)。単変量解析では、NLRはLSSR/180(p=0.006)およびLSSR/365(p=0.009)で予後の有意性を示した。ベースラインのNLR値が7.45以下であることは、180日後の生存率と正の相関があった(感度52%、特異度85.3%、p=0.025)。サブステージbの存在は、早期の進行と180日後の生存率の低下に関連していた(p = 0.031)。貧血は365日後のLSSRを有意に低下させた(p=0.028)。本研究は、犬のDLBCLにおけるPLRとPNRを評価した初めての研究であり、PNRが早期のリンパ腫進行の予測因子となりうることを示している。末梢血細胞の組成は、がん以外のいくつかの原因によって影響を受ける可能性があるため、均質な組み入れ基準を用いた大規模な多施設研究を展開することで、CHOP化学療法を受けた犬のDLBCLにおける血球比率の真の予測値をより明確にすることができるだろう。
犬の腹部骨盤内腫瘍の切除範囲縮小。線量被覆率と正常組織の合併症発生率への影響
画像誘導型強度変調放射線治療(IG-IMRT)は、計画標的体積(PTV)への線量到達率を損なうことなく、リスクのある骨盤内臓器への線量を減少させることができ、マージンの減少により低毒性になる可能性がある。イヌの腹部骨盤腫瘍に対するIG-IMRTでは、適切なPTVマージンが確立されておらず、ここでは、通常のPTV 5mmのマージンがさらに縮小できるかどうかを検討する。非泌尿器系の腹部骨盤内腫瘍に対してIG-IMRTを行い、PTVを5mm拡張した犬のデータセットをこのレトロスペクティブな仮想研究に含めた。臨床的標的体積と危険臓器(OAR)である結腸、直腸、脊髄は、位置決めに使用された各共同登録コーンビームコンピュータ断層撮影(CBCT)に適合させた。新しい治療計画を作成し、PTVマージンを3mmと4mmに縮小して、十分な線量のカバー率とOARの正常組織合併症確率(NTCP)を評価した。10頭の犬に合計70枚のCBCTを撮影した。各CBCTのOARへの線量は、当初計画された線量から軽度に逸脱していた。いくつかの計画では、ボーラスの配置が不十分または欠落していたために、体表面の高線量領域の積み上げが不十分であった。全体として、マージンを4mmまたは3mmに縮小しても線量のカバー率は損なわれず、脊髄遅延性脊髄症を除くすべてのOARでNTCPが有意に低下した。しかし、脊髄に対する全体的なNTCPは非常に低かった(4%未満)。PTV-marginは、患者の固定や治療技術・精度に依存する。IG-IMRTでは、NTCPを最小限に抑えながら、適切な標的線量のカバー率を確保して、腹部・骨盤領域の非常に小さなマージンでの治療が可能である。