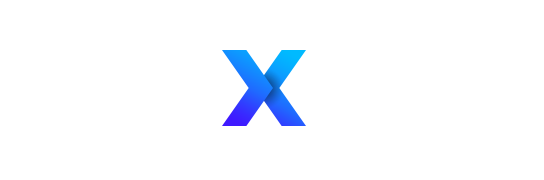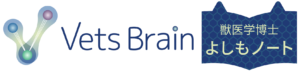皮膚肥満細胞腫(MCT)はイヌの悪性皮膚腫瘍の中で最も頻度の高い疾患である。癌原遺伝子であるc-KITの変異は、MCTの病因および侵襲性と相関している。これまでの研究では、c-KITの変異とKITタンパク質の局在に焦点が当てられており、mRNAレベルの解析はほとんど行われていなかった。本研究では、RNA in situ hybridization(RNA-ISH)により、犬のMCTにおけるc-KITのmRNAの発現を調べた。さらに、c-KIT mRNAの発現と、組織学的グレード、KIT免疫組織化学染色パターン、その他の臨床病理学的パラメータとの関連を評価した。c-KIT mRNAの発現は、すべてのMCTサンプルで観察され、新生物細胞の細胞質内にドットの集まりとして現れた。c-KIT mRNAの発現(Hスコアと陽性細胞の割合により定量化)と組織学的悪性度(2段階および3段階の悪性度分類システムにより判定)の間には、有意な相関関係が認められた。また、c-KIT mRNAの発現と増殖指標(mitotic index、Ki-67、Ag67)との間には、有意な正の相関関係が認められた(いずれもP < 0.05)。しかし、KITの染色パターンの違いに関しては、RNA-ISHによるc-KITの発現との有意な関連は認められなかった。以上の結果から、c-KIT mRNAの発現は、犬の皮膚MCTにおけるc-KITの状態を測定するための追加ツールとなり、潜在的な予後因子として機能する可能性があることが示された。さらなる研究では、犬のMCTの大規模かつ均一なコホートにおいて、c-KIT mRNA発現の予後的意義を評価する必要がある。
犬の乳腺腫瘍。サイズの重要性-低悪性度から高悪性度のサブタイプへの進展
本研究の目的は、乳腺腫瘍の大きさと悪性度の増加との間に考えられる関連性を評価することであった。合計1459の乳腺腫瘍を有する625頭の犬のデータをレトロスペクティブに分析した。80.3%の犬は無傷で、診断時の平均年齢は9.7±2.5歳、75.8%は純血種であった。体重の中央値は20.0kgであった。悪性腫瘍(n=580)は良性腫瘍に比べて有意に大きく(平均でそれぞれ1.94cm対0.90cm;P≦0.0001)、その結果、腫瘍の大きさの増加と良性から悪性への変化との間に正の相関関係が認められた(P≦0.0001;rs=0.214)。悪性腫瘍を4つの悪性度(複合癌/単純癌/固形癌/退形成癌)に分類すると、腫瘍の大きさの増加と悪性度の増加との間に有意な正の相関関係(P ≤ .0001; rs = 0.195)が示された。多くの症例で、悪性度の高い腫瘍が悪性度の低い病変の中に発生していることが認められ、悪性腫瘍のサブタイプの中でさらに進行しているという概念が支持された。複数の腫瘍を有する患者では、悪性腫瘍の平均腫瘍サイズは、1つの腫瘍しか持たない患者に比べて有意に小さかった(平均でそれぞれ1.67 vs 2.71 cm;P < 0.0001)。これらの知見は、乳腺腫瘍が良性から悪性へと進行するだけでなく、低悪性度から高悪性度へと進行することを示唆している。したがって、わずか数ミリの直径の増加が、患者の転帰に大きな影響を与える可能性がある。
犬の肥満細胞腫の外科的マージン評価における光干渉断層撮影法による病理組織検査の可能性と有用性
「獣医における病理組織学的な切除断端の評価は、時間的・経済的な理由から切除断端のごく一部しか評価できない不正確な科学である。犬の肥満細胞腫(MCT)の切除が不完全だと、治療方針や予後が変わってきます。光干渉断層計(Optical Coherence Tomography:OCT)は、新しい画像診断法であり、外科的マージン評価のための単一の獣医学的研究が報告されている。34個のMCTを有する25頭の犬を前向きなパイロット研究に登録し,OCTによる犬のMCTの画像特性を評価し,OCTガイド下の病理組織学の実現性と有用性を評価した。すべての犬は、MCTの定期的な外科的切除を受けた。ホルマリン漬けにする前に、OCT画像を用いて外科的マージン全体を評価した。正常な部位、あるいはMCTの切除が不完全であると疑われる部位のいずれかにインクを塗った。通常の病理組織学的切片とインクを塗った部分の接線切片を作成し,OCTの結果と比較した。26例中10例(38.4%)でOCTにより切除断端付近のMCTが確認された。OCTで不完全なマージンが疑われた4検体では,標準的な病理組織学的切片作成では見逃されたMCTの不完全な切除が行われていた。6検体では、OCTガイド下の切片が疑わしいとされたが、病理組織学的にはMCTを認めなかった。この予備的研究では、OCTガイド下病理切片は、感度90%、特異度56.2%で、手術断端付近のMCTの不完全切除を検出することができた。OCT画像は、犬のMCTを切除した際の外科的マージン評価の診断精度を向上させるために、病理医を関心のある領域に誘導することが期待できる。
浸潤性乳腺癌の犬と猫の1年条件付き生存率。ヒトの乳がんから発想したコンセプト
“イヌとネコの乳腺癌(MC)の予後因子、すなわち診断後の患者の生存を予測する変数については、数多くの研究が報告されている。しかし、癌による早期死亡を免れた患者の生存推定はどのように進化するのでしょうか?ヒトの腫瘍学では、条件付生存(CS)といって、がん患者がすでにY年生存している場合に、さらにX年生存する確率を算出し、長期的な視点でがんの転帰を分析することが行われています。ステージI~IIIの浸潤性MCを外科的に切除した犬344頭と猫342頭のコホートで、最短2年間の追跡調査を行い、1年CS、すなわち1年生存した患者がその後1年間にがんで生存または死亡する確率を算出した。1年間の条件付き特異的生存確率は、イヌとネコで侵襲性MCの診断時にそれぞれ59%と48%、1年間生存したイヌとネコでそれぞれ80%と52%であり、1年間生存したイヌはがんによる死亡から比較的守られているのに対し、ネコのMCは生命を脅かすがんであることが長く続いていることが示唆された。生存している犬と猫のCSに関連する最も重要なパラメータの中には、結節期とリンパ管侵襲があり、生存している犬では、患者の年齢、がんの病期、マージンの状態も同様であった。それに比べて、腫瘍の大きさと組織学的グレードは、生存している犬と猫のCS確率を有意に変えなかった。条件付生存率は、獣医師ががん生存者の転帰を推定するための非常に興味深いツールであると考えられる。
犬の口腔内乳頭状扁平上皮癌の単剤照射による治療-ケースシリーズ
犬の口腔乳頭状扁平上皮癌(COPSCC)は稀な新生物であり、局所浸潤性ではあるが、広い範囲を外科的に切除することで良好な予後が得られる。放射線治療は、外科手術の補助的治療として有効であると報告されている。しかし、単独の治療としての放射線治療の役割については、限られた情報しかない。この単一施設のレトロスペクティブ研究では、マクロスコピックCOPSCCと診断された犬10頭を対象に、単剤で確定的放射線治療(DRT)を行った。これらの犬の年齢の中央値は4歳(範囲:0.4~9.6歳)であった。腫瘍はすべての症例で吻合部の口腔内に存在し、腫瘍サイズの中央値は2.5cm(範囲:0.8~6.8cm)であった。局所および遠隔転移は認められなかった。すべての犬に電子線DRT(>32Gy、3.2Gyのフラクションを1日10~16回)を行った。フォローアップ期間の中央値は961日(範囲:333~3.498日)で、9頭が完全奏効、1頭が部分奏効を得た。部分奏効を示した犬は、放射線治療開始後228日目に病勢が進行した。2頭の犬は腫瘍に関連しない原因で死亡した。残りの7頭は最後の追跡調査の時点で生存しており、完全寛解していた。無増悪生存期間および生存期間の中央値には達しなかった。DRTの忍容性はおおむね良好であったが、すべての犬が自己限定的な急性放射線粘膜炎(グレード2-3)および/または皮膚炎(グレード1)を経験した。晩期放射線毒性は観察されなかった。巨視的COPSCCは放射線感受性の高い腫瘍であり、DRTにより治療が可能であるため、進行した症例では積極的な手術を行う必要がないと思われる。
犬のリンパ腫におけるin vivoでの化学療法効果の可能性を、ex vivoでの薬剤感受性とイミュノフェノタイピングデータを用いて機械学習モデルで予測する
我々は、犬のリンパ腫に対する化学療法剤の有効性の確率を評価するために、ex vivo化学感受性およびイミュノフェノタイピングアッセイと計算モデルを組み合わせた精密医療プラットフォームを報告した。5種類の一般的な化学療法剤(ドキソルビシン、ビンクリスチン、シクロホスファミド、ロムスチン、ラバックフォサジン)のうち少なくとも1種類を投与する予定の犬のリンパ腫患者261名を対象に、罹患したリンパ節の新鮮な細針吸引液から生きたがん細胞を分離し、治療後の臨床反応を収集した。免疫表現型とex vivo化学感受性試験にはフローサイトメトリー解析を用いた。各薬剤について、治療を受けた患者の70%を無作為に選択し、各患者のがん細胞の抗原発現プロファイルや治療感受性の読み取り値などの入力変数に基づいて、Veterinary Cooperative Oncology Group(VCOG)の臨床反応が陽性となる確率を予測するランダムフォレストモデルを学習させました。残りの30%の患者は、モデルの性能をテストするために使用されました。ほとんどのモデルは、テストセットのROC-AUCが0.65を超え、すべてのモデルのROC-AUCは0.95を超えた。反応予測スコアは、B細胞性疾患とT細胞性疾患、新規診断患者と再発患者において、陽性反応と陰性反応を有意に区別した(P < 0.001)。反応予測スコアが50%以上の患者群は、スコアが50%未満の患者群と比較して、完全奏効までの期間が統計的に有意に短縮された(log-rank P < .05)。本研究で開発された計算モデルは、ex vivoの細胞ベースの化学感受性アッセイの結果を、in vivoの治療効果の予測確率に変換することを可能にしました。この計算モデルは、治療効果の肯定的な予測を提供することで、個々の犬のリンパ腫患者の治療結果の改善に役立つと考えられます。
TYMS、HAPLN1、IGFBP5に対する血清自己抗体と早期の犬の悪性乳腺腫瘍との有意な関連性について
犬の乳腺腫瘍(CMT)は、雌犬で最も多く見られる新生物である。このような腫瘍の発生率が高いにもかかわらず、容易に入手できるバイオマーカーがないため、悪性CMTの早期診断が妨げられているのが現状である。ここで我々は、CMT症例において対応する自己抗体を誘発するCMT抗原として、チミジル酸シンテターゼ(TYMS)、HAおよびプロテオグリカンリンクプロテイン1(HAPLN1)、インスリン様成長因子結合タンパク質5(IGFBP5)を同定した。悪性CMT患者81頭(ステージI41頭)、良性CMT患者24頭、健常対照者35頭の血清中のTYMS(TYMS-AAB)、HAPLN1(HAPLN1-AAB)、IGFBP5(IGFBP5-AAB)に対する自己抗体を検出するために、酵素結合免疫吸着法(ELISA)を確立した。悪性CMTでは、3つの自己抗体のレベルが健常者や良性CMTと比較して上昇しており、特にステージIのCMTとの間に有意な相関関係が認められた。悪性CMTと健常対照群との識別において、TYMS-AABの曲線下面積(AUC)は0.694で、特異性は82.9%、感度は50.6%であった。また、HAPLN1-AABを用いたステージI CMTと健常対照者との鑑別のAUCは0.711で、特異度は77.1%、感度は58.5%でした。悪性CMTと良性CMTの鑑別において、IGFBP5-AABのAUCは0.696、特異度70.8%、感度67.9%に達し、IGFBP5-AABとTYMS-AABを併用するとAUCは0.72に増加する。最後に、HAPLN1-AbとIGFBP5-Abの組み合わせによる、ステージIのCMTと良性のCMTの識別のAUCは0.731を達成した。以上のことから、本研究では、3つの血清自己抗体が早期悪性CMTと有意に関連することが明らかになった。
犬のリンパ腫と媒介性疾患。分子学的および血清学的な評価による合併症の可能性
リンパ腫は犬に最も多い血液悪性腫瘍であり、その病因はほとんど分かっていない。リンパ腫の組織に犬の媒介物質(CVBD)が存在することが報告されており、その原因となる影響が疑問視されている。我々は、リンパ腫の犬におけるLeishmania infantum、Ehrlichia canis、Anaplasma phagocytophilum、Bartonella henselaeの感染の有無と程度を評価することを目的とした。リスボン都市圏に住む、リンパ腫と診断された61匹の犬が登録された。血清IgGの検出には、免疫蛍光法を用いた。腫瘍組織におけるCVBD剤のDNAの存在はPCRで評価した。すべての犬でB. henselae、A. phagocytophilum、E. canisは血清検査とPCRの両方で陰性であった。L. infantumについては、8.2%(n=5)の犬で血清学的結果が陽性であった。L. infantumのDNAは、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)の2つのサンプルから検出された。これらの結果は、同じ地域で報告されている犬の集団と比較して、リンパ腫の犬におけるL.infantumの血清陽性率(8.2%対7.9%)および分子検出率(3.3%対1.2%)が、有意ではないが増加していることを示している。今回の調査では、リンパ腫とE. canis、A. phagocytophilum、B. henselae、Leishmania infantumの感染との間に関連性は認められなかった。しかしながら、CVBD疾患の経過を追った更なる研究は価値があり、リンパ腫発生におけるCVBD病原体の役割を明らかにするのに役立つかもしれない。
パピローマウイルスの発癌経路について
パピローマウイルスは発癌性のDNAウイルスであり、ヒトだけでなく多くの家畜や野生動物を含む様々な宿主の皮膚および粘膜組織に過形成の良性病変を誘発する。パピローマウイルスの遺伝子型の中には、牛由来のBPV 1やBPV 2のように、自分とは異なる宿主に感染するものもありますが、これらは馬にも感染し、馬の線維芽細胞性腫瘍の原因となっています。この総説では、病因物質としてのパピローマウイルスの起源と進化を歴史的過程の中でまとめている。この総説では、高リスクのパピローマウイルスのオンコプロテインとプログラムされた細胞死の経路との間の相互作用の評価に主眼が置かれている。さらに、これらの相互作用が悪性細胞の形質転換過程において果たす役割を例示している。これと並行して、パピローマウイルス関連のがんを解明するためのウシのモデルシステムの利用と重要性についても、詳細に検討しています。さらに、トルコの牛群におけるBPV感染症の疫学的状況にも焦点を当てています。
犬の心基底腫瘍の疑いに対する従来の分割照射と定位放射線治療の長期成績
犬の心臓ベースの腫瘍が疑われる場合の放射線治療結果の発表は限られている。このレトロスペクティブな縦断的研究(2014/3~2019)では、心基底部の腫瘤に起因する臨床症状(6)、または心エコー図で腫瘤が徐々に大きくなる無症状(2)のいずれかを有する8頭の犬が、従来の分割放射線治療(CFRT)または定位体放射線治療(SBRT)を受けた。症状のある症例の臨床的所見は、次のうち1つ以上を含んでいました:鼻水・咳(4)、運動不耐性(2)、虚脱(1)、心嚢液貯留(2)、稀な心室性早収縮(2)、腹水(1)、または胸腔液による呼吸困難(1)。CFRTの症例は50Gyを20分割で照射し、SBRTの症例は30Gyを5分割または24Gyを3分割で照射した。2頭の犬は放射線照射後に化学療法を受けた。解析時には7/8頭が死亡し、1頭は治療後684日目に生存していた。初回治療からの推定全生存期間(MOS)中央値は785日(95%CI 114~868日、[範囲114~1492日])であった。5頭の犬がCFRTを受けた(MOS 817日;(95%CI 155日-到達しない[範囲155-1492日]))。3頭の犬がSBRTを受け、1頭は解析時に生存していた(MOS 414日、(95%CI、114日-到達しない[範囲114-414日]))。CFRTとSBRTの生存期間には、統計的に有意な差は認められなかった。症状のある患者のうち、5/6が改善を示した。フォローアップの超音波検査を受けた4/5例では腫瘤のサイズが縮小した。想定される合併症としては、無症候性放射線肺炎(4例)、心房頻拍/早鐘(4例)、腫瘍の進行に伴う心不全を伴う心嚢液貯留(1例)などがあった。この研究は、放射線治療が臨床的に重要な、あるいは進行性に拡大する心底の腫瘤に影響を与える可能性があるという予備的な証拠を提供するものである。