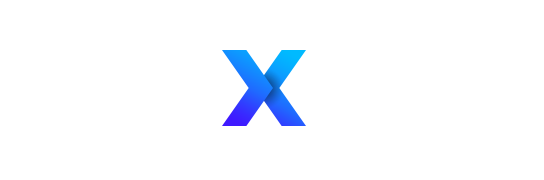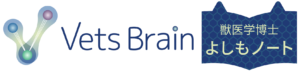化学療法誘発性下痢(CID)は、犬において頻繁に起こる化学療法の有害事象である。しかし、現在のところ、その管理に関するコンセンサスは得られていない。スメクタイトは天然の粘土であり、人間の急性下痢の治療に広く用いられている。本研究の目的は、犬のCID管理におけるスメクタイトの有効性を評価すること、およびCIDに関する疫学データを収集することであった。下痢のエピソードごとに、犬は2つの管理グループに無作為に分けられた。スメクタイト群は、スメクタイトを1日0.5g/kg POを2~3回に分けてCID発症時に投与を開始し、対照群は初期投薬を行わなかった。両群とも、CIDが進行したり、48時間以内に改善されない場合は、レスキュー用のメトロニダゾールが処方された。60頭の犬が募集され、2017年6月から2019年3月までに426回の化学療法投与を受けた。CIDの発生率は110/426(25.8%、95%CI:21.7%~30.2%)で、投与した化学療法薬間で有意差があった(P<0.001)。メトロニダゾールは,スメクタイト群では5/54件(9.3%,95%CI:3.1~20.3%),対照群では40/56件(71.4%,95%CI:57.5~82.3%)に投与された(P < 0.001)。下痢が解消するまでの時間は、スメクタイト群(中央値:19.5時間、四分位範囲[IQR]:13.5~32時間)が対照群(中央値:53時間、IQR:31.5~113.5時間)に比べて短かった(P < 0.001)。本研究の結果は、犬のCIDのファーストライン管理におけるスメクタイトの投与を支持するものである。
上顎骨切除術を受けた猫の転帰:60例。獣医外科腫瘍学会のレトロスペクティブ研究
上顎摘出術は、猫の口腔内腫瘍の治療法としてはあまり報告されておらず、下顎摘出術を受けた猫で報告されている高い合併症率と最適ではない転帰のため、推奨されないこともある。本研究の目的は、上顎骨切除術を受けた猫の合併症と腫瘍学的転帰をレトロスペクティブに評価することである。60頭の猫がこの研究に参加した。上顎摘出術は、片側吻側(20.0%)、両側吻側(23.3%)、分節側(10.0%)、尾側(20.0%)、片側上顎摘出術全摘出(26.7%)であった。術中および術後の合併症は、それぞれ10頭(16.7%)と34頭(56.7%)の猫で報告されました。最も多かった術後合併症は、低酸素症(20.0%)と切開剥離(20.0%)であった。低酸素症の期間の中央値は7日であった。良性腫瘍は19頭(31.7%)、悪性腫瘍は41頭(68.3%)に診断された。局所再発率は18.3%、転移率は4.9%であり、無増悪期間(PFI)の中央値には達しなかった。疾患関連生存期間の中央値は、全体でも、良性腫瘍でも悪性腫瘍でも到達しなかった。1年および2年生存率は、良性腫瘍の猫ではそれぞれ100%および79%、悪性腫瘍の猫では89%および89%、線維肉腫の猫では94%および94%、扁平上皮癌の猫では83%および83%、骨肉腫の猫では80%および80%であった。予後不良因子としては、PFIでは分裂指数、PFIと生存期間の両方では補助化学療法、生存期間では局所再発が挙げられた。上顎骨切除術は猫にとって有効な治療法であり、良好な局所腫瘍制御と長い生存期間が得られる。
犬の腫瘍におけるエンドグリン発現のリアルタイムRT-PCRを用いた血管新生の再現性のある客観的評価法
血管新生療法は、新しい血管の形成を標的としたがん治療戦略です。微小血管密度(MVD)は、血管新生を評価するための病理組織学的手法であり、エンドグリンはヒトの医療において活性化内皮マーカーとして使用されています。MVDを用いた治療効果の評価は、再現性のない方法であるため困難である。そこで,再現性のある血管新生評価法を開発するために,MVD,内皮マーカーおよび血管新生因子のmRNA転写レベルの相関関係を調べ,組織サンプルとFNA(fine needle aspiration)で得られた微小サンプルの間でmRNA転写レベルの一致を確認した。51頭の犬から様々な種類の自然発症の腫瘍が採取された。MVDはvWF(von Willebrand factor)の免疫染色で評価した。vWF、エンドグリン、VEGF(vascular endothelial growth factor)、VEGF receptor-2(VEGFR2)のmRNA転写レベルは、リアルタイム逆転写ポリメラーゼ連鎖反応(real-time RT-PCR)を用いて分析した。MVDとvWF、エンドグリン、VEGFR2のmRNA転写レベルには、有意な相関関係が見られた。VEGFR2は、vWF(P <.01, Rs = 0.512)よりもエンドグリン(P <.01, Rs = 0.649)との相関が強く、エンドグリンのmRNA転写レベルを測定することで、より正確に血管新生を評価できることが示された。また、組織とFNAサンプルのmRNA転写レベルは強く相関しており、FNAサンプルを用いた血管新生の評価が可能であることが示唆された。以上、FNA採取による内皮マーカーのmRNA転写レベルを用いた、再現性のある客観的な血管新生評価法を開発した。
両側乳房切除術を受けた乳腺癌の猫における周術期デスモプレッシンの効果
デスモプレシンの周術期投与は、グレードIIおよびIIIの乳腺癌を有する犬において、局所再発および転移の割合を有意に減少させ、生存期間を延長することが示されている。本研究の目的は、両側乳房切除術にデスモプレシンの周術期投与を行った場合と行わなかった場合の、乳腺癌の猫の腫瘍学的転帰を比較することである。9つの動物病院の医療記録を検索し、両乳房切除術を受けた乳腺がんと診断された猫を特定した。単発または段階的な両側乳房切除術を受けた60頭の猫を対象とした。デスモプレシンを投与した猫としなかった猫の間で、腫瘍学的転帰に有意な差は認められなかった。周術期にデスモプレシンを投与した猫には、副作用は認められなかった。術後合併症は、単発の両側乳房切除術を受けた猫18頭(38.3%)と、段階的な両側乳房切除術を受けた猫3頭(23.1%)に発生した(P = 0.48)。組織学的グレードと、提案された5段階の組織学的ステージングシステムの修正版は、ともに無病期間の予後を左右した。組織学的に不完全な切除は,転移や腫瘍の進行の割合が有意に高く,生存期間中央値(MST)の短縮と関連していた。また、局所再発を起こした猫では、MSTが有意に短かった。本研究の結果は、猫の乳腺癌の治療のために両側の乳房切除を行う際に、転帰を改善するために周術期にデスモプレシンを使用することを支持するものではない。
中~高悪性度非ホジキンリンパ腫の犬における治療前の血漿Dダイマー値の予後評価
治療前のD-ダイマーレベルは、ヒトの患者のいくつかのタイプの悪性腫瘍における生存を予測することが報告されている。本研究の目的は、中~高悪性度非ホジキンリンパ腫(NHL)のイヌにおいて、治療前のDダイマー値の予後を評価することである。F14512とリン酸エトポシドを比較したプロスペクティブな無作為二重盲検試験において、中~高グレードのNHLと診断された48頭の顧客所有の犬を対象に、治療前の血漿Dダイマー値の予後を評価した。治療前の血漿Dダイマー値と、様々な臨床的特徴、無増悪生存期間(PFS)および全生存期間(OS)との相関関係を分析しました。治療前の血漿Dダイマー濃度の中央値は0.4μg/mL(範囲:0.1~14.3μg/mL)であった。治療前の血漿Dダイマー値が高い(0.5μg/mL以上)犬は44%(21/48)に認められた。D-ダイマーの高値は、リンパ腫の初期と再発、臨床病期、サブステージ、免疫表現型、治療群とは相関していなかった。0.5μg/mL以上のD-ダイマー値は、PFS(54日対104日、P=0.011)およびOS(93日対169日、P=0.003)の中央値の低下と有意に関連していた。多変量解析では、Dダイマーの高値は依然としてPFS(HR:3.21、95%CI:1.57-6.56、P = 0.001)およびOS(HR:3.87、95%CI:1.88-7.98、P < 0.001)の悪化の独立した予測因子であった。本研究では、中~高悪性度NHLの犬において、治療前の血漿Dダイマー値が予後の予測因子となることが示唆された。これらの所見を確認するためには、さらなる研究が必要である。
多中心性リンパ腫の犬における初回化学療法時の体重変化と臨床転帰の関連性
リンパ腫の犬における既知の予後因子の大部分は、治療開始前または診断時に評価されている。治療の初期段階で評価された予後因子はあまり記述されていないが、重要な臨床情報を提供する可能性がある。このレトロスペクティブ研究では、82頭の犬のリンパ腫患者を、診断時と5週間の化学療法後の体重変化に応じて分類した。初期体重の5%以上の増加または5%以上の減少を示した犬は、それぞれ体重増加群または体重減少群に分類された。体重の変化が5%未満の犬は体重維持群に分類した。体重増加群、体重維持群、体重減少群の無増悪生存期間(PFS)の中央値は、それぞれ226日、256日、129日であった。体重減少群は、体重増加群および体重維持群に比べて、PFSが有意に短かった(それぞれP = 0.023、P = 0.003)。体重増加群、体重維持群、体重減少群の生存期間(ST)の中央値は、それぞれ320日、339日、222日であった。3群間のSTには有意な差はなかった(P=0.128)。Cox回帰の結果、体重変化群と初期体重はPFSに関連する有意なリスク因子であったが(それぞれP=0.007、P=0.001)、患者の初期体重のみがSTに関連する有意なリスク因子であった(P=0.013)。結論として、多中心性リンパ腫の犬では、初期体重と体重の経時的変化を評価することで、PFSとSTに関する貴重な情報を得ることができる。
絶食は犬におけるビンクリスチン関連の有害事象の発生を抑制する
絶食は、インスリン様成長因子(IGF-1)の減少を介して、化学療法に関連する有害事象(AE)を減少させることが示されており、マウスや人において化学療法治療中の正常細胞に対する保護効果を誘発する可能性がある。本研究の目的は、ビンクリスチンを投与されているイヌにおいて、断食が体質、骨髄、消化管(GI)のAE、および血清グルコース、IGF-1、インスリン濃度に及ぼす影響を評価することであった。本試験は、腫瘍を有する犬を対象としたプロスペクティブ・クロスオーバー臨床試験であった。犬は、初回または2回目のビンクリスチン投与前の24~28時間および投与後の6時間は絶食し、代替投与では通常の食事を与えるように無作為に割り付けられた。空腹時には、吐き気、食欲不振、嗜眠、血清インスリンの有意な減少が認められたが、その他のGI症状、好中球数、血清グルコース、IGF-1には有意な差は認められなかった。ビンクリスチン投与前の絶食は、安全で効果的な治療法であり、担癌犬の体質的およびGI AEを軽減するのに役立った。
悪性卵巣腫瘍の犬18頭の治療成績に関するレトロスペクティブ分析
悪性卵巣腫瘍の犬の予後に関しては、ほとんど証拠がない。このレトロスペクティブな研究の目的は、悪性卵巣腫瘍の犬の、補助療法を伴うまたは伴わない手術を含む治療後の転帰を記述し、予後因子を決定することであった。対象となった犬は18頭で、年齢の中央値は12歳(範囲:7~15歳)、体重の中央値は6.9kg(範囲:2.3~17.8kg)であった。病理組織学的診断によると、顆粒膜細胞腫が最も多く(n=9)、次いで異種細胞腫(n=5)、腺癌(n=4)であった。11頭の犬が単独で手術を受けた。7頭は手術に加えて、化学療法や放射線療法などの補助療法を行った。卵巣腫瘍に起因する死亡のみを考慮した場合、生存期間(ST)の中央値は1009日であり、ST中央値の予測因子は、単変量解析において、Tカテゴリー(T3以上、443日 vs T2以下、1474日;P = 0.002)、転移病変の存在(存在する、391日 vs 存在しない、1474日;P < 0.001)、リンパ管腔浸潤(存在する、428日 vs 存在しない、1474日;P = 0.003)であった。顆粒膜細胞腫瘍の犬のSTの中央値は、異種細胞腫や腺癌の犬よりも長く感じられたが、その差は統計的には有意ではなかった(それぞれ1474日対458日;P = 0.10)。良好な予後を考慮すると、悪性卵巣腫瘍の犬、特に早期の症例には積極的な治療が推奨できる。診断時に転移があったにもかかわらず、転移のある犬の半数は1年以上生存していた。
miR-497は、犬の乳腺腫瘍においてIRAK2/NF-κB軸によるアポトーシスを誘導する
コンパニオン・ドッグは人間と同じ生活環境を持っているため、人間の病気を研究するのに適した動物モデルであり、特に犬の自然発生的な乳腺腫瘍モデルについてはその傾向が強い。犬の乳腺腫瘍の自然史と分子メカニズムの理解を深めることは、比較医学において大きな意義がある。ここでは、犬の乳腺腫瘍症例を収集し、その臨床例を病理学的検査とHE染色およびIHCによる分類によってアッセイした。 miRNA-497ファミリーメンバー(miR-497、miR-16、miR-195、miR-15)は、乳がんマーカー遺伝子p63およびPTENと正の相関関係があった。犬の乳腺腫瘍細胞株CMT1211およびCMT7364において、miR-497の発現を調節すると、アポトーシスが誘導され、細胞の増殖が抑制された。メカニズム的には、IRAK2が、NF-κB経路の活性を阻害することでがん細胞の特性に影響を与えるmiR-497の機能的な標的であることが示された。以上のことから、犬の乳腺腫瘍の進行には、miR-497/IRAK2/NF-κBの軸が重要な役割を果たしていることが明らかになり、この軸が乳がんのターゲットになることが示唆された。