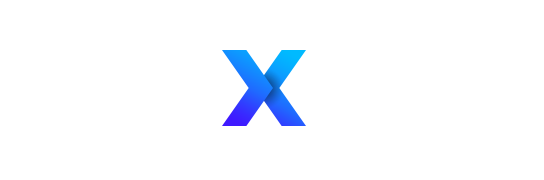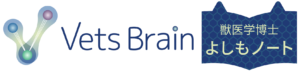犬の原発性肺癌(PPC)のステージ分類は、1980年に最終更新された。人では、ヒト肺癌ステージ分類(HLCSC)(現在第8版)が診断と治療の意思決定に不可欠な役割を果たしており、異種の腫瘍集団にもかかわらず予後を決定している。このレトロスペクティブなケーススタディの目的は、犬のPPCに適用しやすいようにサブステージを削除してHLCSCから適合させた犬の肺がんステージ分類(CLCSC)の予後的意義を評価することである。副次的な目的は、術後補助化学療法の効果を評価することであった。組織学的に確認されたPPCの犬71頭の医療記録を検討した。すべての犬は、原発性肺腫瘍の外科的切除を受けた。原発性腫瘍の特徴(T1~T4ステージを参照)とTNMステージ(1~4)は、CLCSCを用いて割り当てられた。犬の肺癌の病期はI(n=7)、II(n=32)、III(n=24)、IV(n=8)であった。生存期間の中央値は、I~IV期でそれぞれ952日、658日、158日、52日であった。原発性腫瘍の特徴(T1-T4)、外科的切除の不完全性、リンパ節転移の有無、腫瘍のグレードが全生存期間の独立した予後指標であった。26頭の犬が術後補助化学療法を受けたが、統計的に有意な効果は認められなかった。CLCSCの原発腫瘍の特徴とステージ分類は、PPCの犬の生存に対して高い予後を示した。我々は、犬のPPCステージ分類に対するこの更新の更なる適用と評価を提案する。進行期の犬のPPCの予後が悪いことを考えると、新しい治療法が必要である。
脈管侵襲のない副腎小腫瘍に対する副腎摘出術を受けた犬の治療成績
獣医学的な研究では、犬の副腎摘出術の結果が報告されているが、これらの研究では一般的に、脈管侵襲の有無を含めた様々なサイズの副腎腫瘍が対象となっている。本研究の目的は、組織学的に確認された脈管侵襲のない小型副腎腫瘍を副腎摘出術で治療した犬のコホートにおける転帰を報告することである。このレトロスペクティブ研究は、2010年から2017年にかけてフロリダ大学とカリフォルニア大学デービス校のデータベースのデータを用いて行われた。最大径≦3cmの副腎腫瘍の切除を受けた犬で、コンピュータ断層撮影で評価したどの部位にも脈管侵襲の証拠がない場合を対象とした。51匹の犬が組み入れ基準を満たした。副腎摘出術を受けた犬の短期生存率は92.2%,1年間の疾患特異的生存率は83.3%であった。51頭中28頭(54.9%)が悪性腫瘍と診断された。軽度の合併症は、術中および術後によく観察された。重大な合併症は6頭に認められ、突然死、呼吸停止、急性腎不全、出血、低血圧、誤嚥性肺炎などであった。短期死亡は4頭であった。死亡に至る主要な合併症としては、突然死と出血が最も多かった。副腎摘出術は、これまでに報告された周術期死亡率の高さから議論を呼ぶこともあるが、本研究の結果は、血管侵襲のない小さな腫瘍に対する副腎摘出術が低リスクで実施できることを裏付けている。
犬の胃組織におけるTn抗原とシアリルTn抗原
悪性腫瘍の変化は、タンパク質のグリコシル化の異常と関連していることが多く、特に単純なムチン型糖鎖であるTn抗原やシアリルTn(STn)抗原の蓄積によって表現される。これらの抗原は通常、正常組織では限られており、その発現量の増加は癌の進行や予後の悪化と関連している。本研究では、犬の胃粘膜の腫瘍化におけるTn抗原とSTn抗原の役割を評価し、それらの免疫発現の変化を病理学的特徴と関連付けることを目的としている。犬の正常胃粘膜(n = 3),胃ポリープ(n = 9),胃癌(n = 25),腫瘍性塞栓(n = 12),転移(n = 8)において,Tn抗原とSTn抗原の発現を免疫組織化学的に評価した。正常な胃粘膜では、Tn抗原は胃上皮細胞に検出されたが、STn抗原は検出されなかった。同様に,胃ポリープはすべてTn抗原を発現していたが,STn抗原の免疫染色を示すものはなかった。癌腫では、Tn抗原は96%、STn抗原は68%に発現していた。STn抗原は正常粘膜と比較して癌で有意に高かった(P < 0.05)。各抗原と、WHO分類による腫瘍のサブタイプの違い、腫瘍の分化、リンパ管侵襲、転移との間には相関関係は認められなかった。すべての腫瘍性塞栓物は両抗原を発現しており、その発現スコアは原発腫瘍の腫瘍性細胞が示すものと同等かそれ以上であった。STn抗原が正常粘膜と比較して胃癌で高頻度に発現していることは、この抗原の癌関連性を強調するものである。今回の結果は、STn抗原の発現が新生物の変化と関連しており、イヌの胃がん進行の有用なマーカーとなる可能性を示唆している。
頭頸部癌におけるセンチネルリンパ節検出のための間接CTリンパグラフィープロトコルの開発と他のセンチネルリンパ節マッピング技術との比較
「転移性疾患の同定は、新生物患者の治療と予後に決定的な影響を与える。腫瘍リンパを流すセンチネルリンパ節または第一リンパ節を同定するための複数の技術が存在する。センチネルリンパ節を特定することで、リンパ節転移を判定するための正確な組織採取が可能となる。本研究の目的は、頭頸部に腫瘍を持つ犬のセンチネルリンパ節を同定するためのコンピュータ断層撮影(CT)プロトコルを開発することであった。また、CTによる間接的なリンパ節撮影を、リンパシンチグラフィーおよびバイタル色素注入と比較し、どちらの手法がより確実にセンチネルリンパ節を特定できるかを検討した。ヨード化造影剤の胸腔内注入によるCT間接リンパ撮影では,18頭中8頭で排液リンパ管が確認され,18頭中5頭でセンチネルリンパ節が確認された。ヨード化した造影剤の4象限周囲注入を用いたCT間接リンパ撮影では、20頭中18頭で排液リンパ管を同定し、20頭中11頭でセンチネルリンパ節を同定した。バイタル色素注入法とリンパシンチグラフィでは,それぞれ18頭中17頭,20頭中20頭でセンチネルリンパ節が同定された。識別されたセンチネルリンパ節は、原発腫瘍の同側または両側にあった。どちらのCT技術も安全で簡単であることがわかった。CTを用いて様々な頭頸部癌のセンチネルリンパ節を検出するためには、腫瘍周囲注射が最も有望であり、一方、リンパシンチグラフィは比較した技術の中で最も成功していた。
2台の犬用頭蓋内位置決めシステムを用いた放射線治療における画像誘導の有無によるセットアップエラー
デイリーイメージガイダンスは、頭蓋内放射線治療における患者の位置のフラクショナル間変動を低減する。しかし、ポジショニングエラーを検出して修正する能力は、あるレベル以下に制限されています。このため,画像誘導前の位置決めシステムの精度が,画像誘導後に残る誤差(残留セットアップ誤差)に影響を与える可能性がある。本研究の目的は,2つの頭蓋内位置決めシステムを用いて,メガボルテージ(MV)およびコーンビームコンピュータ断層撮影(CBCT)による画像誘導の前後で得られるセットアップ精度を比較することである。装置には、1mmの並進移動が可能な4自由度のカウチが含まれていました。6頭の犬の死体を臨床治療のように24回、頭部再配置装置(HPS)に配置し、画像誘導による補正の前後に5つのフィデューシャルマーカーの座標を測定した。HPSで得られた値を,当施設で使用している標準ポジショニングシステム(SPS)で既報の値と比較した。3次元距離ベクトル(3DV)の平均値は,画像誘導を行わなかった場合のSPSよりもHPSの方が低かった(P = 0.019)。MVガイド後の平均3DVは,HPSの方がSPSよりも低かったが(P=0.027),CBCTガイド後には差がなかった(P=0.231)。MVガイド後とCBCTガイド後の3DVの95%値は、HPSではそれぞれ2.1mmと2.9mm、SPSでは2.8mmと3.6mmであった。MVガイド後のセットアップエラーは,画像ガイド前に患者の位置をより正確に達成したポジショニングシステムの方が低かった。
猫の副鼻腔癌に対する最終的な放射線治療。多施設でのレトロスペクティブな評価
猫の上皮性副鼻腔腫瘍の治療はあまり報告されていない。新しい報告では、緩和的な放射線治療が確定的な治療よりも多く報告されている。この多施設のレトロスペクティブ研究では、シングルモダリティ放射線治療を受けた27頭の猫を対象とした。猫には1日10回、4.2Gyの放射線を照射した。その結果、3頭(11.1%)が完全な臨床反応を示し、17頭(63%)が部分的な臨床反応を示した。また、3頭(11.1%)の猫で臨床症状の安定が認められた。4頭(14.8%)の猫が治療後3カ月以内に進行した。全症例の進行までの期間の中央値は269日(95%信頼区間[CI]:225;314)であった。1年後および2年後に進行が認められなかった猫の割合は、それぞれ24%(95%CI:22%;26%)および5%(95%CI:5%;6%)であった。評価された予後因子はいずれも転帰を予測するものではありませんでした(貧血、ステージング時の腫瘍体積、修正Adamsステージ、頭蓋内病変、顔面変形、鼻出血、不摂生、体重減少)。全死亡例の全生存期間(OS)中央値は452日(95%CI:334;571)であった。1年後および2年後に生存していた猫の割合は、それぞれ57%(95%CI:37%;77%)および27%(95%CI:25%;29%)であった。意外なことに、鼻出血のある猫はOSの中央値が828日(95%CI:356;1301)と、鼻出血のない猫の296日(95%CI:85;508)に比べて長かった(P = 0.04、Breslow)。猫の副鼻腔癌の治療に放射線療法を単独で用いると、臨床症状が改善し、忍容性も高いが、1年以内に進行することが多い。
犬の辺縁帯リンパ腫と濾胞性リンパ腫のトランスクリプトーム、メチルーム、コピー数異常データの統合解析
限界帯リンパ腫(MZL)と濾胞性リンパ腫(FL)は、犬の低悪性度B細胞リンパ腫に分類される。犬の低悪性度B細胞リンパ腫の一つである。我々は、トランスクリプトーム、ゲノム全体のDNAメチル化、コピー数異常の解析を統合して、犬のMZL(n = 5)とFL(n = 7)の病因を明らかにし、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)と比較した。トランスクリプトームプロファイリングの結果、BCRやTLRのシグナル伝達経路など、両組織型に共通する生物学的プロセスの存在が明らかになった。しかし、FLはE2F標的の濃縮を示したのに対し、MZLはMYCによる転写活性化の特徴を示した。FLはCEACAM23と24を含むchr1に特徴的な欠損を示したが、逆にMZLはMYCが存在するchr13に複数の反復した欠損を示した。メチル化ピークの分布は、2つのタイプの間で類似していた。3つのオミックスから得られたデータを統合すると、FLはMZLやDLBCLのデータセットから明確に分離された。MZLは、FoxM1ネットワークとTLR関連のTICAM1依存のIRFs活性化経路の濃縮を示した。しかし、MZLとDLBCLを区別する特定のシグネチャーはなかった。結論として、本研究は、犬のFLおよびMZLの分子的およびエピジェネティックな病因を初めて包括的に解析したものである。
犬の多中心性非低悪性度T細胞リンパ腫の臨床病理学的特徴と予後因子:107例
犬のリンパ腫は、最も一般的な造血器悪性腫瘍として、異質な疾患群を包含しており、T細胞の免疫表現型の中でも、臨床症状や治療への反応に違いが存在する。このレトロスペクティブな研究の目的は、多中心性の非低悪性度T細胞リンパ腫(TCL)の犬107頭に対して、ロムスチンを用いた治療(70%)とロムスチンを用いない治療(30%)を行い、その結果と予後因子を明らかにすることである。大半はラブラドール、ボクサー、混血犬、ドグ・ド・ボルドーであった。86%がサブステージb、77%が縦隔浸潤、15%が骨髄浸潤の疑い、12%がその他の結節外病変部位を有していました。導入療法に対する全奏功率は80%で、導入プロトコールでプロカルバジンを投与された犬(P=0.042)、好中球濃度が8.7×10e9/L以下(P=0.006)、有糸分裂率が5ハイパワーフィールドあたり10以下(P=0.013)の犬は奏功率が高かった。最初の寛解における無増悪生存期間(PFS)の中央値は105日で、フローサイトメトリーでのCD3の発現がないこと(P < 0.0001)とステロイドによる前処理(P = 0.012)は、PFSの短縮と有意に関連していた。CD79aの共発現(P = 0.002)、フローサイトメトリーでのCD3発現の欠如、貧血の存在(P = 0.007)、単細胞減少(P = 0.002)は、OSTの短縮を予測していた。犬における多中心性の非低悪性度TCLは、新しい予後因子の可能性がある攻撃的な癌である。
犬の悪性粘膜メラノーマにおけるLong interspersed nucleotide element-1 hypomethylation
犬の悪性黒色腫は、死亡率の高い一般的な癌であり、臨床的にも重要な疾患である。DNAメチル化は、遺伝子の転写を抑制するプロモーター領域での異常なDNAメチル化を介して、潜在的な腫瘍発生メカニズムであると考えられている。また、全体的なメチル化低下は、染色体の不安定性を促進する可能性もある。犬の悪性黒色腫におけるDNAメチル化に関する報告はほとんどないため、本研究の目的は、この疾患におけるゲノム全体のメチル化変化のサロゲートマーカーとして、長散在性ヌクレオチド要素-1(LINE-1)のDNAメチル化状態を調べることであった。我々は、犬のメラノーマ患者41例および6つの細胞株を対象に、正常粘膜と比較して、LINE-1配列の推定プロモーターにあるCpGアイランド(CGI)上の隣接する2つのシトシン-グアニン部位のDNAメチル化レベルをバイサルファイト-パイロシークエンスにより測定した。生存率は飼い主や医療記録から得た。その結果、正常粘膜におけるLINE-1のDNAメチル化レベルが判明した。興味深いことに、メラノーマ細胞株と臨床メラノーマサンプルの両方で、顕著な低メチル化が見られました。さらに、LINE-1のメチル化度が低い患者は、LINE-1のメチル化度が高い患者よりも予後が悪いことがわかったが、その差は統計的有意差には達しなかった(P = 0.09)。以上のことから、犬のメラノーマにおいて、LINE-1の低メチル化はエピジェネティックに異常な特徴であり、予後を左右する可能性があることがわかった。
脾臓血管肉腫の犬におけるEGFビスペシフィックアンギオトキシン(eBAT)のドキソルビシン化学療法の間隔を狭めての反復投与の影響
我々は以前、EGFを標的としたアンギオトキシンであるeBATが安全であることを報告し、脾臓血管肉腫の犬に対して、標準治療に加えて3回の投与を1サイクルとした場合、最小残存病変の設定で全生存期間を改善しました。SRCBST-2試験の目的は、eBATを複数サイクル投与することで、忍容性が高く、eBATの効果をさらに高めることができるかどうかを評価することでした。試験の対象は、ステージ3の血管肉腫の犬で、肉眼的病変を外科的に切除できる犬に拡大されました。eBATから化学療法開始までの期間を短縮し、実験的治療を3サイクルに拡大した。生物学的に活性な用量(50μg/kg)を脾臓摘出後の月・水・金のスケジュールで投与し、1回目、2回目、5回目のドキソルビシン化学療法の1週間前に予定した。25頭の犬が登録され、6頭が急性低血圧を起こし、2頭が入院を要した。また、1頭の犬に自己限定的なALTの上昇が認められた。本試験では、eBAT治療を受けた犬は、標準治療のみを受けたステージ1~3の血管肉腫の犬の同時代比較群と比較して、統計学的に有意な生存率の向上は認められませんでした。この結果から、eBATをドキソルビシン化学療法の1週間前から繰り返し投与すると、手術と化学療法の開始を遅らせる間に1サイクル投与した場合に比べて、毒性が強くなり、有効性が低下することがわかりました。犬の血管肉腫やその他の腫瘍に対するeBATの臨床効果を最大限に高めるためには、eBATの正確な作用メカニズムを理解する必要がある。IACUCプロトコル:1110A06186および1507-32804A。